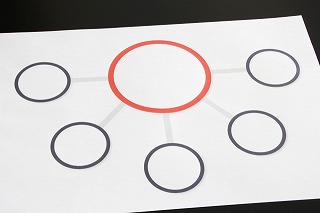「優秀な監理技術者がいるが、一つの現場にしか配置できず、他の案件が受けられない…」
「監理技術者補佐を置けば兼務できると聞いたけど、具体的な条件は?」
「ICTを使えば、遠隔地でも兼務は可能なの?」
こんなお悩みを抱えていませんか?
ご安心ください。
その悩みは、建設業法が定める監理技術者の「兼務」に関する特例ルールを正しく理解することで、解決への道筋が見えてきます。
この記事では、原則として兼務が認められない専任の監理技術者が、例外的に複数の現場を管理するための3つの具体的な方法について、分かりやすく解説します。
建設業界において、特定建設業許可を取得し、大規模な元請工事を手掛ける企業にとって、優秀な「監理技術者」の確保と、その効果的な配置は、経営の根幹を揺るがす最重要課題です。
建設業法は、大規模で社会的な影響の大きい工事の品質と安全を確保するため、監理技術者を現場ごとに「専任」で配置することを原則として義務付けています。
この「専任」とは、他の現場との兼務を禁止することを意味するため、「一人の監理技術者は、一つの現場しか担当できない」というのが長年の大原則でした。
しかし、深刻な技術者不足や建設業界のDX化といった時代の変化に対応するため、近年、この原則にはいくつかの重要な「緩和措置(特例)」が設けられています。
今回は、企業の生産性向上と人材の有効活用に直結する、監理技術者が複数の現場を兼務するための3つの合法的な道筋について、詳しく見ていきましょう。
1なぜ監理技術者の兼務は、より厳しく制限されるのか?
まず、なぜ監理技術者の兼務が、主任技術者に比べてより厳しく制限されているのかを理解しておく必要があります。
主任技術者の場合、「密接な関係のある2以上の工事」であれば、比較的容易に兼務が認められます。しかし、監理技術者にはこの規定が原則として適用されません。
これは、監理技術者が配置される現場が、多数の下請負人を統括し、より高度で複雑な施工管理を要する大規模工事であるためです。
工事全体の品質・安全に対する責任がより重いため、一つの現場に集中することが強く求められているのです。
2監理技術者の兼務を可能にする3つの特例
この厳しい原則に対し、法律は以下の3つのケースにおいて、例外的に監理技術者の兼務を認めています。
2-1. 特例①:「監理技術者補佐」を専任で配置する方法
これが、監理技術者の兼務を実現するための最も代表的で、活用しやすい制度です。2020年(令和2年)の法改正で導入されました。
⑴ 制度の概要:
それぞれの工事現場に、監理技術者を補佐する「監理技術者補佐」を専任で配置することを条件に、一人の監理技術者が「最大2つまで」の工事現場を兼務することが認められます。
⑵ 監理技術者補佐の資格要件:
監理技術者補佐になることができるのは、1級の国家資格者等(監理技術者の資格を持つ者)または、1級技術検定の第一次検定に合格した者(1級技士補)です。
高い専門性が求められます。
⑶ 活用のポイント:
この制度により、企業は、最も経験豊富なトップクラスの技術者(監理技術者)の知見を、複数の重要案件に活かすことが可能になります。
監理技術者補佐の育成も同時に進めることができ、企業全体の技術力向上にも繋がります。
2-2. 特例②:一体性のある複数工事を「一つの工事」とみなす方法
これは、主任技術者の場合と同様に、監理技術者にも適用される考え方です。
⑴ 制度の概要:
発注者が同一で、契約工期が重複する複数の請負契約であっても、それらの工事対象が、客観的に見て「同一の施設」や「連続する一体の工作物」であると認められる場合は、全体を「1つの工事」とみなし、一人の監理技術者が担当することができます。
⑵ 具体例:
①一つの庁舎ビルについて、「建築工事」と「電気設備工事」と「管工事」が別々に発注された場合。
②連続する道路改良工事が、複数の工区に分けて契約された場合。
⑶ 活用のポイント:
この特例を適用する際は、工事の一体性について発注者と共通の認識を持ち、できればその旨を書面で確認(事前承諾)しておくことが、後のトラブルを避ける上で非常に重要です。
2-3. 特例③:ICT活用による兼務(現在検討が進む新しい形)
ユーザー様ご提供の本文にあった複数の要件は、この新しい兼務の形に関連するものです。
建設DXの進展に伴い、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔での現場管理を条件に、さらなる兼務の緩和が検討・試行されています。
これは、例えばウェアラブルカメラやドローンなどを活用し、監理技術者が遠隔地にいながら、現場の状況をリアルタイムで把握し、適切な指示を行うことを想定したものです。
この適用の可否や具体的な要件(現場間の距離、連絡員の配置など)は、現時点ではまだ一般的ではなく、個別の工事ごとに発注者や許可行政庁との綿密な協議が必要となる、先進的な取り組みと位置づけられます。
将来的に、これが技術者不足解消の切り札となることが期待されています。
3整理
監理技術者の「専任」義務は、建設工事の品質と安全を守るための重要なルールです。
しかし、法律は同時に、深刻化する技術者不足に対応し、生産性を向上させるための、現実的で合理的な「兼務」の道も示しています。
特に「監理技術者補佐」制度は、多くの特定建設業者にとって、人材を有効活用し、事業機会を拡大するための強力な武器となり得ます。
自社の技術者の資格や経験、そして受注する工事の特性を見極め、これらの特例制度を正しく理解し、計画的に活用していくこと。
それが、これからの時代を勝ち抜く建設業経営に求められる、重要な戦略と言えるでしょう。
4まとめ
監理技術者の「兼務」に関するルールは、複数の特例が絡み合う、非常に専門的で複雑な領域です。
しかし、その正しい活用は、企業の生産性と競争力を大きく左右します。
「自社の技術者体制で、兼務は可能なのか」「監理技術者補佐制度を導入したいが、どうすれば良いか」といったお悩みは、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令に基づき、貴社の事業戦略に合わせた最適な技術者配置をご提案します。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、貴社の「無限の可能性」を法務面から力強く支援いたします。
5お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/