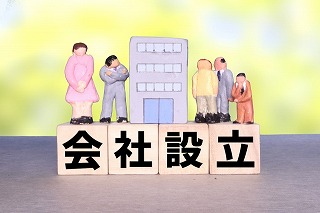「医療法人の設立準備中だが、役員や社員は誰でもいいのだろうか?」
「MS法人の役員が、医療法人の役員を兼任しても大丈夫だろうか?」
岩手・宮城、東北のクリニック経営者の皆様、このような疑問をお持ちではありませんか?
そのお悩み、本記事でスッキリ解決できます。
役員・社員の資格要件には、医療法や指導要綱に基づく厳格なルールが存在し、見落とすと設立認可が下りない可能性もあります。
今回は、医療法人の役員・社員の資格要件と、特にトラブルになりやすいMS法人との兼務について、専門家の視点で分かりやすく解説します。
1 医療法人の「社員」とは?その役割と資格要件
まず、医療法人における「社員」とは、株式会社でいう「株主」に近い存在です。
クリニックで働くスタッフ(職員)のことではありません。
社員は、医療法人の最高意思決定機関である「社員総会」の構成員となり、法人の運営に関する重要事項(役員の選任・解任、定款変更、予算・決算の承認など)について議決権を行使します。
1-1. 「名目的な社員」は認められない
社員は、法人の意思決定に実質的に参画する重要なポジションです。
そのため、単に名前を貸しているだけ、あるいは議決権を行使する能力や意思がない人物(例:認知症の高齢者など)が、名目的に社員に選任されている状態は、ガバナンスの観点から「適切ではない」と厳しく指導されます。
1-2. 未成年者の社員就任について
未成年者であっても、自分の意思で議決権を行使できる程度の「弁別能力(物事を判断できる能力)」を備えていれば、社員になること自体は可能とされています。
ただし、その判断は非常に曖昧であり、社員総会の決議の有効性に関わる問題に発展するリスクもあるため、実務上は慎重な判断が必要です。
1-3. 出資持分と社員資格の関係
出資持分の定めのある医療法人(平成19年3月31日以前に設立)において、相続などによって出資持分の「払戻請求権(金銭的な価値)」を得た場合でも、注意が必要です。
医療法人の運営管理指導要綱では、金銭的な権利を相続したからといって、自動的に「社員としての資格(議決権)」も継承できるわけではない、とされています。
社員になるためには、あくまで上記1-1のような社員としての資格要件を備えている必要があります。
1-4. 設立時の社員と役員(理事)の関係
理事(役員)は、社員以外の者から選任することも理論上は可能です。
しかし、現実的には、法人の運営を担う理事は、法人の最高意思決定機関のメンバーである社員の中から選任されるのが通常です。
特に、医療法人「設立時点」での最初の社員は、そのまま最初の役員(理事)に就任することが一般的です。
したがって、設立時の社員は、後述する「役員の資格要件」も同時に満たしている必要があります。
2 医療法人の「役員(理事・監事)」の選任と資格要件
医療法人の役員(理事および監事)は、社員総会の決議によって選任されます。
役員には、医療法によって厳格な「欠格事由」が定められています。
2-1. 理事の資格要件と欠格事由
医療法人の理事には、以下のいずれかに該当する者は就任できません。
① 法人 (理事は自然人(個人)でなければなりません)
② 成年被後見人 または 被保佐人 (十分な判断能力を有することが求められます)
③ 医療法、医師法、歯科医師法等の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
④ 上記(3)以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
これらの欠格事由は、医療の公共性・非営利性を担保するために設けられています。
2-2. 理事長の資格要件
理事長は、理事会において理事の中から選出されますが、極めて重要な要件があります。
〇 原則として、医師または歯科医師である理事から選出すること
これは、医療法人が医療専門家によって管理されることを担保する規定です。
また、理事長は法人の業務執行を統括する重責を担うため、複数の医療法人の理事長を兼務することは、管理運営の集中・徹底の観点から不適当とされています。
2-3. 監事の資格要件と「成り手不足」の問題
監事は、理事の業務執行や法人の財産状況を監査する重要な役割を担います。
そのため、理事とは独立した立場であることが強く求められます。
監事は、当該医療法人の理事や職員(院長、事務長など)を兼ねることはできません。
(医療法第48条)
さらに、多くの都道府県の指導要綱では、監査の独立性・中立性を確保するため、以下のような人物も監事として就任することは「適当でない」とされています。
① 当該医療法人の顧問税理士、顧問弁護士
② 当該医療法人の役員と親族関係にある者
③ 当該医療法人と取引関係のある業者
これらの人々は、法人と利害関係があり、客観的な監査が期待できないと見なされるためです。
県によっては、「簿記2級以上の資格保持者であること」といった、より具体的な能力要件を課している場合もあります。
この「監事の独立性」の要件が、実務上、多くの医療法人を悩ませる「監事の成り手不足」問題を引き起こしています。
信頼できる第三者で、かつ医療法人の監査を担える人物を見つけるのは容易ではありません。
3 最重要!MS法人との関係と役員兼務の「5つの条件」
個人開業医の先生方が医療法人化(法人成り)する際、最も注意すべき点の一つが「MS法人」との関係です。
MS法人(メディカル・サービス法人)とは、医療法人が行えない営利業務(不動産賃貸、医療機器のリース、経理・清掃業務の受託など)を行うために設立される、医師やその親族が経営する株式会社などの「営利法人」を指します。
3-1. なぜ役員の兼務が厳しく制限されるのか?
問題は、医療法人が「非営利性」を求められるのに対し、MS法人は「営利性」を追求する点にあります。
もし、医療法人の理事長が、MS法人の社長も兼務していたらどうなるでしょうか?
その人物は、医療法人からMS法人へ業務を委託する際、MS法人の利益を最大化する(=医療法人に高額な委託料や賃料を支払わせる)ような契約を結ぶかもしれません。
これは「利益相反」行為であり、医療法人の非営利性を著しく損なうため、医療法人運営管理指導要綱によって、MS法人の役員が、医療法人の理事長や役員(理事)になることは、原則として「適当でない」とされています。
3-2. 役員兼務が「例外的」に認められる5つの条件
とはいえ、小規模なクリニックでは、経営者がMS法人の役員も兼ねざるを得ない実態もあります。
そのため、規制が一部緩和され、現在では以下の「5つの条件すべて」を満たす場合に限り、例外的に役員の兼務が認められるようになりました。
① 兼務する役員が、医療法人の「代表者(理事長)」でないこと。
② 営利法人(MS法人)の規模が小さく、役員を変更することがすぐには困難であること。
③ 医療法人とMS法人の間の契約内容(賃料、委託料等)が、市場価格に照らして妥当であること。
④ その契約が、医療機関の非営利性に影響を与えないと判断されること。
⑤ 医療法人とMS法人の取引額が、医療法人の事業収益と比較して少額であること。
3-3. 設立認可申請時は「特に厳しいチェック」が入る
このMS法人との関係は、医療法人設立認可申請の際に、行政(県や保健所)が最も厳しくチェックするポイントの一つです。
「例外が認められるなら大丈夫だろう」と安易に判断してはいけません。
多くの県では、MS法人との取引がある場合、設立申請時にMS法人の登記事項証明書、定款、株主名簿、そして両社間の取引契約書(不動産賃貸契約書、業務委託契約書など)のすべての提出を求められます。
その内容を精査され、「利益相反の恐れあり」と判断されれば、認可が保留または不認可となるリスクが非常に高いのです。
4 まとめ
医療法人の設立、役員変更、そしてMS法人との適正な関係構築。
これらは、医療経営において非常に専門的かつ複雑な手続きを伴います。
「何から手を付けていいか分からない」「本業の診療が忙しく、書類作成まで手が回らない」というのが、多くの先生方の本音ではないでしょうか。
そのような時こそ、専門家である行政書士にご相談いただくことで、「トータルで任せる安心感」を手に入れることができます。
行政機関への対応は、独自のルールやローカルな指導基準も多く、非常に煩雑です。専門家である行政書士にご依頼いただくことで、これらの手続きを迅速かつスムーズに進めることが可能になります。
当事務所では、多忙な医師・歯科医師の皆様、医療事務の皆様のサイドに寄り添い、現状を丁寧にヒアリングした上で、最善の解決策をご提案いたします。
当事務所の最大の特徴として、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他士業と強力な連携体制を組んでおり、設立後の労務問題や税務、万が一のトラブルにもワンストップで対応が可能です。
さらに、代表者は元岩手県職員として、企業立地や県立大学新設といった大型プロジェクトの行政調整業務に従事した経験を有しております。
この経験から、国(地方厚生局)や県、各保健所といった行政機関の思考や手続きの進め方を熟知しており、迅速かつ的確な調整・対応ができる点は、他にはない「強み」であると自負しております。
初回のご相談は無料です。
岩手県・宮城県をはじめ東北全域の医療機関様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
【注意事項】
厚生労働省(地方厚生局)や県、各保健所への「医療法人設立認可申請」や「各種届出」について、報酬を得て他人の依頼を受け、必要な申請などを代理することは、行政書士法に基づき、行政書士にのみ認められた独占業務です。
行政書士以外の者(無資格のコンサルタントなど)がこれらの業務を行うことは、法律で禁止されています。
5 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/