
こんな悩みはありませんか?
「建設業の許可って、自分の会社に必要なの?」
「新規で許可を取りたいけど、何から手をつければいいか…」
「更新の時期が迫っているけど、手続きが面倒…」
「専門用語が多くて、許可のことがよく分からない!」
「岩手県で建設業許可に詳しい専門家を探している」
その悩みは今回の説明で解決できます
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必須の許可です。
しかし、その種類や要件、申請手続きは複雑で、多くの方が頭を悩ませています。
この記事では、建設業許可について、初めての方にも分かりやすく徹底解説します。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します
岩手県北上市を中心に、建設業許可の新規取得・更新をサポートする行政書士が、許可の種類、必要な要件、申請の流れ、注意点などを詳しく解説。
あなたの疑問や不安を解消し、スムーズな許可取得をサポートします!
1.建設業許可、なぜ必要?~法的義務と事業成長の鍵
「建設業許可」は、単なるお役所手続きではありません。
建設業法という法律で定められた義務であり、建設業を営む上で避けて通れない重要なステップです。
なぜ建設業許可が必要なのか?
その理由は、大きく分けて2つあります。
(1)建設工事の品質確保:
建設工事は、人々の生活や安全に深く関わるものです。
もし、技術力のない業者や、手抜き工事をする業者が工事を行えば、重大な事故につながる可能性があります。
建設業許可制度は、一定の基準を満たした業者だけに許可を与えることで、工事の品質を確保し、国民の安全を守る役割を担っています。
(2)発注者の保護:
建設工事は、高額な費用がかかることが多く、発注者にとって大きなリスクを伴います。
建設業許可制度は、許可業者の情報を公開することで、発注者が安心して業者を選べるようにする役割も果たしています。
許可業者は、経営状況や技術力などを審査されているため、一定の信頼性が担保されていると言えます。
*許可が不要な「軽微な建設工事」とは?
建設業法では、小規模な工事については、許可がなくても施工できると定めています。
これを「軽微な建設工事」と言います。
(3)建築一式工事:
1件の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(木造住宅とは、主要構造部が木造で、2分の1以上を居住の用に供するもの)
(4)建築一式工事以外:
1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
注意点として、
-請負金額には、消費税が含まれます。
-元請が材料を提供する場合でも、その材料費は請負金額に含めて判断します。
-複数の工事をまとめて請け負う場合、合計金額で判断します。
-軽微な工事に該当するかどうかは、個別のケースによって判断が異なる場合があります。-不明な場合は、必ず専門家(行政書士など)や行政に相談しましょう。
2.【一般】と【特定】、2種類の建設業許可 ~ 下請契約の規模で使い分け
建設業許可は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類に分かれています。
この違いは、主に「下請契約の規模」によって決まります。
(1)一般建設業許可
・特徴:
発注者から直接工事を請け負う(元請)場合、下請に出す金額に制限はありません。
下請として工事を行う場合は、金額に関わらず、一般建設業許可でOKです。
小規模~中規模の工事に適しています。
・具体例:
個人住宅の新築・リフォーム
小規模な店舗の改修
アパート・マンションの建設(下請として参加する場合)
(2)特定建設業許可
・特徴:
元請として工事を請け負い、かつ、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる場合に必要です。
大規模な工事で、多くの下請業者を使う場合に必要となります。
特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可よりも厳しい要件(財産的基礎、技術力など)を満たす必要があります。
・具体例:
大規模なマンション・ビルの建設
公共施設の建設(道路、橋梁、ダムなど)
下請代金の考え方
下請代金の総額には、消費税が含まれます。
元請が下請に材料を提供する場合、その材料の価格は下請代金に含めません(建設業許可事務ガイドライン第3条関係4)。
これは、軽微な工事の判断(材料費を含む)とは異なる点なので、注意が必要です。
複数の下請業者に工事を発注する場合、下請代金の総額で判断します。
下請契約が複数ある場合は、それらすべてが、同一の建設工事について締結されたものでなければなりません。
〇具体例で確認
あなたが建設会社を経営していて、
1億円の商業ビル建設工事(建築一式工事)を受注。
そのうち、A社に基礎工事を4,000万円、B社に内装工事を3,000万円で下請に出す。
この場合、下請代金の総額は7,000万円になるので、特定建設業許可が必要です。
〇なぜ特定建設業許可が必要?
大規模な工事では、多数の下請業者が関わるため、元請には、下請業者を適切に管理・監督する責任があります。特定建設業許可は、特に高い管理能力や財産的基礎を持つ業者にのみ許可を与えることで、下請業者や労働者の保護を図ることを目的としています。
3.無許可営業はダメ!【重い罰則】に注意 ~ 建設業法違反のリスク
建設業許可が必要な工事を無許可で行ったり、許可の範囲を超えた工事を請け負ったりすると、建設業法違反となり、厳しい罰則が科せられます。
これは、建設業界の秩序を守り、悪質な業者を排除するための重要なルールです。
(1)罰則の種類
・無許可営業:
建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負った場合。
・許可条件違反:
一般建設業許可しか持っていないのに、特定建設業許可が必要な規模の工事を請け負った場合。
許可を受けた業種以外の工事を請け負った場合。
(2)罰則の内容
・個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)
・法人:1億円以下の罰金(建設業法第52条)
(3)罰則以外
罰則を受けるだけでなく、以下のような不利益を被る可能性もあります。
①社会的信用の失墜:
取引先や金融機関からの信用を失い、今後の事業活動に大きな影響が出ます。
②入札参加資格の喪失:
公共工事の入札に参加できなくなる可能性があります。
③損害賠償請求:
工事に欠陥があった場合、発注者から損害賠償を請求される可能性があります。
(4)「知らなかった」は通用しない
建設業法違反は、「知らなかった」では済まされません。
建設業を営む上で、許可制度について正しく理解し、適切に対応することが不可欠です。
4.建設業許可【29の業種】を詳しく解説!~ 自社に必要な許可を見極める
建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。許可を取得する際は、自社が行う工事の種類に合わせて、必要な業種の許可を取得する必要があります。
◆29業種は、
①・区分:一式工事
・建設工事の種類:土木一式工事、建築一式工事
②・区分:専門工事(27業種)
・建設工事の種類:大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(1)業種区分の重要性
①適切な許可の選択:
自社が行う工事の種類に合わない許可を取得しても、意味がありません。
例えば、内装工事しか行わないのに、土木一式工事の許可を取得しても、内装工事の許可としては使えません。
②許可条件の確認:
業種ごとに、許可を取得するための要件(技術者の資格、実務経験など)が異なります。
自社が満たすべき要件を正確に把握する必要があります。
(2)業種選択の注意点
①複数の業種に該当する場合:
自社が行う工事が複数の業種に該当する場合は、それぞれの業種の許可を取得する必要があります。
②将来の事業展開も考慮:
現在は特定の業種しか行っていなくても、将来的に事業を拡大する可能性がある場合は、関連する業種の許可も取得しておくことを検討しましょう。
5.【一式工事】って何?他の工事との違い ~ 総合的なマネジメントの役割
「一式工事」とは、土木一式工事と建築一式工事の2つを指します。
これらの工事は、規模が大きく、複数の専門工事を組み合わせて行う必要があるため、総合的なマネジメント(企画、指導、調整)が必要となる工事です。
(1)一式工事の定義
①土木一式工事:
トンネル、ダム、道路、橋梁など、大規模な土木工作物を建設する工事。
複数の専門工事(例:とび・土工・コンクリート工事、舗装工事、しゅんせつ工事など)を組み合わせて行うことが多い。
②建築一式工事:
住宅、マンション、ビル、商業施設など、建築物を新築・増改築する工事。
複数の専門工事(例:大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事など)を組み合わせて行うことが多い。
(2)一式工事のポイント
①元請としての役割:
一式工事は、原則として、元請として工事全体を請け負う場合に必要となる許可です。
元請は、工事全体の計画、工程管理、品質管理、安全管理など、総合的なマネジメントを行います。
②下請との関係:
下請業者が「一式工事」を請け負うことは、原則としてありません(一括下請負の禁止)。
下請業者は、元請から依頼された専門工事(例:大工工事、電気工事など)を個別に請け負います。
「一式工事の許可があれば、どんな工事でもできる!」と誤解している人がいますが、それは間違いです。
①専門工事は別:
専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要です。
例えば、壁紙の張り替え工事だけを請け負う場合、「建築一式工事」の許可ではダメで、「内装仕上工事」の許可が必要になります。
②許可の使い分け:
一式工事は、あくまで「総合的なマネジメント」を行うための許可です。
個別の専門工事の技術力や資格は、別途必要になります。
6.建設業の「許可票」【掲示は義務!】~ 見やすい場所に、正しく表示
建設業許可を取得したら、「許可票」(通称:金看板)を作成し、営業所と工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。
これは、建設業法で定められた義務であり、違反すると罰則の対象となる場合があります。
(1)許可票の役割
①許可業者であることの証明:
建設業許可を受けていることを対外的に示すことで、発注者や関係者に安心感を与えます。
②建設業法の遵守:
許可票の掲示は、建設業法を遵守していることの証でもあります。
③不正業者の排除:
許可票の掲示がない業者は、無許可営業の可能性があります。
(2)許可票に記載する内容
①営業所:
一般建設業又は特定建設業の別
許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
商号または名称
代表者の氏名
②工事現場:
一般建設業又は特定建設業の別
許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
商号または名称
代表者の氏名
主任技術者または監理技術者の氏名
(3)許可票のサイズ
根拠:建設業法施行規則 第二十五条
営業所:縦35cm以上 × 横45cm以上
工事現場:縦25cm以上 × 横35cm以上
(4)許可票の材質
法律上の規定はありません。
紙、プラスチック、金属など、どんな材質でも構いませんが、耐久性のあるものが望ましいです。
(5)許可票の様式
建設業法施行規則で定められた様式(フォーマット)に従う必要があります。
建設業法施行規則第25条第2項で、店舗と現場とで、様式(表形式)が定められています。
許可票に、自由にデザインや写真などを入れることはできません。
(6)掲示場所
①営業所:
公衆の見やすい場所(入口付近、受付など)に掲示します。
②工事現場:
工事関係者だけでなく、一般の通行人など、誰でも見やすい場所に掲示します。
工事現場の入口付近、仮囲いなどに掲示するのが一般的です。
(7)その他
許可票は、許可の有効期間中、継続して掲示する必要があります。
許可内容に変更があった場合は、許可票の記載内容も変更する必要があります。
許可票を紛失したり、破損したりした場合は、再発行の手続きが必要です。
7.建設業許可【申請手続きの流れ】
建設業許可の申請手続きは、大きく分けて以下の流れになります。
・事前準備:必要書類の収集、申請書の作成など
・申請:許可行政庁(岩手県知事許可の場合は、管轄の広域振興局など)に申請書類を提出
・審査:提出された書類に基づいて、許可要件を満たしているか審査
・許可:審査を通過すると、建設業許可証が交付
8.建設業許可【必要書類】は?
建設業許可の申請には、多くの書類が必要です。主なものは以下の通りです。
・建設業許可申請書
・役員等の一覧表
・営業所一覧表
・専任技術者証明書
・実務経験証明書(専任技術者になる場合)
・経営業務の管理責任者証明書
・財務諸表
・納税証明書
・登記簿謄本(法人の場合)
・身分証明書、登記されていないことの証明書(個人事業主の場合)
・その他(許可行政庁が求める書類)
*注意!
上記は一般的な必要書類です。
申請内容や許可行政庁によって異なる場合があります。
書類の有効期限にも注意が必要です(例:納税証明書は発行から3ヶ月以内など)。
原本が必要な書類と、コピーで良い書類があります。
申請書類は、正本1部、副本(コピー)1部以上を提出するのが一般的です。
9.建設業許可【取得のメリット】
建設業許可を取得すると、以下のようなメリットがあります。
①事業拡大のチャンス:
500万円以上の工事を請け負えるようになり、より大きなビジネスチャンスをつかむことができます。
②社会的信用が向上:
建設業許可は、一定の基準を満たした業者にのみ与えられるため、顧客や取引先からの信頼が高まります。
金融機関からの融資が受けやすくなるなど、資金調達の面でも有利になります。
③公共工事の入札に参加できる可能性:
多くの公共工事では、建設業許可が参加資格の要件となっています。
公共工事を受注できれば、安定した収入源を確保できるだけでなく、会社の知名度アップにもつながります。
④コンプライアンスの強化:
建設業法を遵守することにより、適正な経営を行うことにつながります。
10.【岩手県版】建設業許可申請のポイント
岩手県で建設業許可を申請する際のポイントをまとめました。
・申請窓口:
岩手県知事許可:主たる営業所の所在地を管轄する広域振興局
国土交通大臣許可:主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局(岩手県の場合は、東北地方整備局)
・申請手数料:
知事許可:新規9万円、更新5万円
大臣許可:新規15万円、更新5万円
・その他:
岩手県では、建設業許可申請の手引きをホームページで公開しています。最新情報を確認しましょう。
-岩手県「建設業許可申請の手引き」:
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kensetsu/kyoka/1019730.html
-申請前に、広域振興局等に事前相談することも可能です。
-参考:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
11.まとめ
建設業許可は、取得することでビジネスチャンスを大きく広げることができる、非常に重要な許可です。
しかし、その申請手続きは複雑で、専門的な知識も必要になります。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
12.お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1)お問い合わせフォーム
(2)事務所ホームページ<許認可申請>

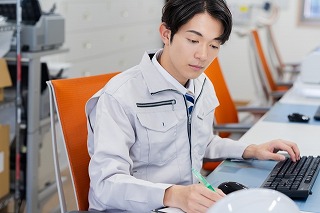


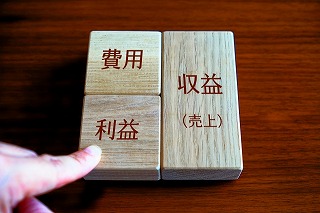

.jpg)