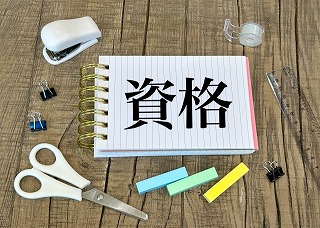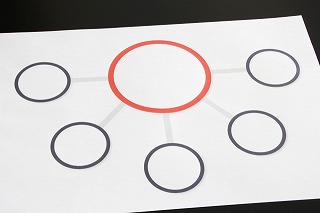「営業所にいる技術者に、現場の主任技術者も兼務させたい…」
「複数の現場を、一人の営業所技術者で見ることはできないだろうか?」
「そもそも、営業所技術者と現場技術者の兼務は、どこまでが適法なの?」
こんな疑問を感じていませんか?
ご安心ください。
その疑問は、建設業法が定める技術者の「常勤」と「専任」のルールを正しく理解することで解決できます。
この記事では、多くの経営者様が悩む「営業所技術者」と「現場技術者」の兼務について、その可否を判断するための3つのケース別に分かりやすく解説します。
建設業を営む上で、技術者の確保と適切な配置は、経営の根幹をなす非常に重要なテーマです。
特に、限られた人材で事業を運営する中小の建設業者様にとっては、「営業所にいる技術者と、現場に出る技術者を、一人の有資格者で兼務させることはできないか?」という問いは、極めて切実なものでしょう。
しかし、この「兼務」の問題は、建設業法における「営業所技術者」と「主任技術者・監理技術者」のそれぞれの役割と、法律が求める「常勤」「専任」という概念を正確に理解していなければ、意図せず法令違反に陥ってしまうリスクをはらんでいます。
今回は、この複雑な技術者の兼務ルールについて、その核心を詳しく見ていきましょう。
1大原則:「営業所技術者」と「現場の技術者」は別の役割
まず、なぜ兼務が原則として難しいのかを理解するために、二つの技術者の役割の違いを押さえておく必要があります。
1-1. 営業所技術者(旧:専任技術者)の職務
営業所技術者は、その名の通り、営業所に常勤することが義務付けられています。
その主たる職務は、営業所内で行われる請負契約の見積もり、入札、契約締結といったプロセスにおいて、技術的な観点から適正性を確保することです。
いわば、契約業務における「技術的な司令塔」の役割を担います。
近年では、常時連絡が取れる体制であれば、テレワークによる勤務も「常勤」として認められるようになりました。
1-2. 主任技術者・監理技術者の職務
一方、主任技術者・監理技術者は、工事現場に配置され、その工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理など、現場における「技術上の管理」を行うのが主たる職務です。
いわば、現場の「安全と品質の責任者」です。
このように、勤務場所も主たる職務も異なるため、原則として一人の技術者が両方の役職を同時に担うことはできない、というのが法律の基本的な考え方です。
2ケース別解説
原則は兼務不可ですが、一定の条件下では例外的に兼務が認められています。
その判断は、現場に「専任」が求められる工事かどうかで、大きく分かれます。
2-1. ケース①:「専任」が求められない工事での兼務
まず、技術者の「専任」配置が求められない工事、つまり請負代金4,500万円(建築一式は9,000万円)未満の工事の場合です。
この場合、平成15年4月の国土交通省の通知により、以下の3つの要件をすべて満たせば、営業所技術者がその現場の主任技術者を兼務することが認められています。
① その営業所において契約を締結した工事であること。
② 工事現場と営業所が、地理的に近接していること。
③ 営業所と工事現場との間で、常時、電話などで連絡を取りうる体制にあること。
ここで注意すべきは、「近接している」という距離について、法律上一律の基準はないという点です。
これは、各地域の交通事情などに応じて個別に判断されるため、不安な場合は事前に許可行政庁に確認するのが賢明です。
2-2. ケース②:「専任」が求められる工事での兼務
次に、請負代金4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の、技術者の「専任」配置が求められる重要な工事の場合です。
この場合、営業所技術者が現場の専任技術者を兼務することは、原則として認められません。
なぜなら、専任技術者はその工事に専従し、常時継続的に現場の職務に集中することが求められるからです。
しかし、ここにも例外的な緩和措置が存在します。
ユーザー様ご提供の本文にあった複数の条件は、主にこの緩和措置に関するものですが、その適用は非常に限定的です。
例えば、特定の工事(契約工期が余裕を持って設定され、かつ工事現場の相互間の距離が近いなど)において、発注者の承諾を得た上で、限定的に兼務が認められるケースがありますが、その判断は極めて慎重に行われます。
安易に「兼務できる」と自己判断するのは非常に危険です。
2-3. ケース③:所属営業所と現場の場所の関係
最後に、兼務とは別の論点ですが、重要なポイントです。
営業所技術者はその営業所に常勤する必要がありますが、現場に配置される主任技術者・監理技術者は、必ずしもその工事を契約した営業所に所属している必要はありません。
例えば、盛岡市の本社に所属するAさんが、北上市の支店が受注した工事現場の主任技術者になることは、Aさんが会社と直接的・恒常的な雇用関係にあれば、何ら問題ありません。
会社全体として、技術者を柔軟に配置することが可能です。
3整理
営業所技術者と現場技術者の兼務ルールは、一見すると複雑です。
しかし、その根底にあるのは、「営業所の技術的な拠点機能」と「工事現場の技術的な管理機能」という、二つの重要な役割をそれぞれ確実に果たさせる、という考え方です。
「この工事は兼務できるのか?」と判断に迷った時、その基準となるのは、まず「専任が求められる工事かどうか」です。
その上で、それぞれのケースに定められた要件をクリアしているかを慎重に確認する必要があります。
このルールを正しく理解し、遵守することは、法令違反のリスクを回避するだけでなく、限りある有能な技術者を、企業全体として最も効率的に配置・活用していくための鍵となるのです。
4まとめ
建設業における技術者の配置、特に「営業所技術者」と「現場技術者」の兼務ルールは、解釈が複雑で、誤った運用は許可の維持に関わる重大な問題に発展しかねません。
「自社の技術者配置は、法的に問題ないだろうか」「もっと効率的な人員配置はできないか」といったお悩みは、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、最新の法令に基づき、貴社のコンプライアンス遵守と、効率的で力強い事業運営の両立をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
5お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/