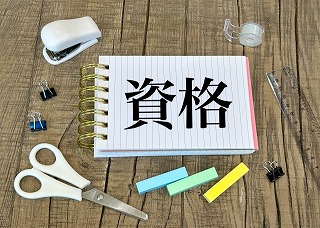「有能な技術者をもっと有効活用したい…」
「A現場の主任技術者に、近くのB現場も兼務させることはできないだろうか?」
「法律が厳しくて、技術者の配置にいつも頭を悩ませている…」
こんなお悩みを持つ経営者様はいらっしゃいませんか?
ご安心ください。
そのお悩みは、建設業法が定める技術者の「専任」と「兼務」のルールを正しく理解することで、解決への道筋が見えてきます。
この記事では、主任技術者・監理技術者が、複数の工事現場を適法に兼務するための具体的なケースについて、分かりやすく解説します。
建設業界における深刻な技術者不足は、多くの企業の経営を圧迫する大きな課題です。
限られた人材をいかに効率的に配置し、生産性を高めていくか。
その鍵の一つが、主任技術者や監理技術者の「兼務」に関するルールの正しい理解です。
「一人の技術者は、一つの現場にしか配置できない」という原則はよく知られていますが、実は、時代の変化や働き方改革の流れを受け、法律は一定の条件下で、技術者が複数の現場を兼務する道を認めています。
今回は、企業の可能性を広げる、この「兼務」のルールについて詳しく見ていきましょう。
1大原則:「専任」が求められる工事では兼務はできない
まず、全ての基本となる原則を確認します。
公共性のある施設や、多数の人が利用する施設に関する重要な建設工事(※)では、工事現場ごとに技術者を「専任」で配置することが義務付けられています。
この「専任」とは、他の工事現場との兼務を禁止し、常時継続的にその現場の職務にのみ従事することを意味します。
したがって、この専任義務がある工事においては、原則として、一人の主任技術者・監理技術者が他の工事現場を兼務することはできません。
※請負代金4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事が対象
しかし、この大原則には、いくつかの重要な「例外」が設けられています。
2例外①:「専任」が求められない工事現場での兼務
最も基本的な兼務が可能なケースは、そもそも技術者の「専任」が求められない工事現場です。
つまり、請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)に満たない工事であれば、建設業法上、主任技術者の兼務を直接禁止する規定はありません。
この場合、一人の主任技術者が複数の現場を兼務することは可能ですが、それはあくまで、それぞれの現場で求められる職務(施工管理、品質管理、安全管理など)を適切に遂行できる、ということが大前提となります。
3例外②:「専任」が必要な工事でも兼務が認められる特例ケース
技術者不足という深刻な課題に対応するため、法律は、専任が求められる工事であっても、一定の条件下で兼務を認める特例を設けています。
3-1. ICT活用による兼務(専任特例1号)
近年のDX技術の進展を背景に、情報通信技術(ICT)を活用して遠隔で現場管理を行うことを条件に、兼務が認められるようになりました。具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 2つの工事現場のいずれにも、監理技術者補佐を配置すること。
② 2つの工事現場間の距離が10km程度と、近接していること。
③ 兼務する監理技術者が、ICT機器(ウェアラブルカメラなど)を活用し、常時、遠隔で各現場の状況を把握・指示できること。
この特例は、主に監理技術者を対象としていますが、技術者を有効活用する上での新しい流れと言えます。
3-2. 密接な関係のある複数工事での兼務
同一の建設業者が、同一の場所、または近接した場所において施工する、相互に密接な関連のある2つ以上の建設工事については、同一の主任技術者・監理技術者が兼務することができます。
〇 「密接な関係」の例:
・2つの工事の資材を一括で調達し、相互に工程を調整しながら進める場合。
・関連する工事の大部分を、同一の下請負人が施工する場合。
・「近接した場所」の目安:
明確な定義はありませんが、一般的に10km程度の距離が目安とされています。
3-3. 一体性のある工作物に関する複数契約での兼務
発注者が同じで、契約工期が重複する複数の請負契約であっても、それらの工事対象が、同一の建築物や、連続する一体の工作物である場合は、全体を「1つの工事」とみなし、同一の主任技術者が兼務することができます。
例えば、一つのビルについて、「躯体工事」と「設備工事」が別々の契約になっていたとしても、これらは一体の工事と見なされ、一人の主任技術者が両方を管理することが可能です。この場合、発注者との間での書面による合意が望ましいとされています。
4特別な制度:専門工事一括管理施工制度
これは技術者の「兼務」とは少し異なりますが、限りある人材の有効活用という観点から創設された重要な制度です。
元請が配置する主任技術者(または監理技術者)が、一定の要件を満たす特定の専門工事(現在は鉄筋工事と型枠工事)について、下請負人が本来配置すべき主任技術者の職務を併せて行うことができる、というものです。
この制度を活用することで、対象となる下請負人は、自社の主任技術者を配置する必要がなくなります。
この制度の適用には、下請金額の上限(4,500万円未満)や、元請技術者の資格・経験、発注者の書面による承諾など、複数の厳しい要件がありますが、重層下請構造の生産性を向上させるための画期的な仕組みとして注目されています。
5整理
主任技術者・監理技術者の兼務に関するルールは、原則と多くの例外が組み合わさった、非常に複雑な体系となっています。
しかし、これらの緩和措置や特例は、深刻化する技術者不足に対応し、建設業界の生産性を向上させるために設けられたものです。
これらのルールを正しく、そして深く理解し、自社の状況に合わせて適切に活用していくこと。
それが、法令を遵守しつつ、企業の競争力を高め、持続的な成長を遂げるための鍵となるのです。
6まとめ
建設現場における技術者の配置、特に「兼務」のルールは、解釈が複雑で、自己判断は大きなリスクを伴います。
しかし、そのルールを正しく活用すれば、企業の人材をより効率的に運用し、生産性を高めることも可能です。
「自社のこのケースでは、技術者の兼務は認められるだろうか」「最新の緩和措置について、詳しく知りたい」など、技術者配置に関するお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令に基づき、貴社のコンプライアンスと経営効率を両立させる、最適な技術者配置をご提案します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/