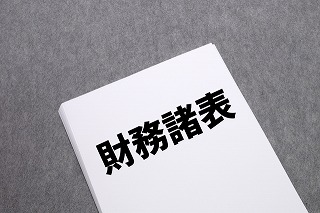「500万円以上の工事を請け負いたいけど、どの業種の許可が必要なの?」
「自社の工事は、どの業種に該当するんだろう?」「許可業種と違う工事を請け負ってしまったら…?」
こんなお悩みはありませんか?
建設業許可を申請するにあたって、自社が行う、あるいはこれから行う「建設工事」が、どの業種に該当するのか、その概要を具体的に知っておくことは非常に重要です。
許可業種と工事内容が一致しないと、最悪の場合、建設業法違反となる可能性もあります。
ご安心ください。
今回の記事では、建設業許可における「工事の種類(業種)」の正しい判断方法を、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
この記事を読めば、自社の工事に必要な許可業種が明確になり、安心して事業を進められるようになります。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で建設業を営む皆様、ぜひ最後までお読みください。今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。(全角319文字)
1なぜ重要?建設業許可と工事の種類(業種)の関係
建設業許可は、建設業法に基づき、建設工事を請け負う事業者に義務付けられている制度です。
この許可制度は、工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進することを目的としています。
そして、この建設業許可は、29種類の「建設工事の種類(業種)」ごとに取得する必要があります。
つまり、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1500万円以上)を請け負うためには、その工事の種類に応じた許可が必要となるのです。この金額未満の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可は不要です。
1-1. 許可業種と工事内容の不一致はNG!:違反するとどうなる?
建設業許可制度において、最も注意すべき点の一つが、許可業種と請け負う工事内容の不一致です。
例えば、「とび・土工・コンクリート工事」の許可しか持っていない建設業者が、500万円以上の「舗装工事」を請け負うことはできません。
これは、建設業法違反(無許可営業)となり、罰則や行政処分の対象となる可能性があります。
具体的には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科せられる可能性があります(建設業法第47条)。
さらに、指示処分や営業停止処分、最悪の場合は許可の取消しといった行政処分を受ける可能性もあります(建設業法第28条、第29条)。
許可が取り消されると、その後5年間は新たな許可を取得できなくなるなど、事業継続に大きな影響を及ぼします。
また、無許可営業は、公共工事の入札参加資格を喪失する原因にもなります。
入札参加資格を失うと、公共工事を受注できなくなり、事業の機会を大きく失うことになります。
さらに、建設業者の社会的信用も失墜し、取引先や金融機関からの信頼を失うことにもつながりかねません。場合によっては、発注者から損害賠償を請求される可能性もあります。
1-2. 元請だけでなく下請も注意!:下請への影響と元請の責任
業種判断の重要性は、自社が元請として工事を請け負う場合だけでなく、下請業者に工事を発注する場合にも及びます。下請業者に工事を発注する際には、発注する工事の内容が、下請業者の許可業種と合致しているかを確認する義務が元請業者にあります。
もし、無許可業者に工事を発注してしまうと、元請業者も建設業法違反に問われる可能性があります。これは、建設業法が、元請業者に対して、下請業者の選定や指導監督について、一定の責任を課しているためです。
具体的には、元請業者は、下請業者と契約を締結する際に、下請業者の許可証を確認し、許可業種と工事内容が一致しているかを確認する必要があります。
また、工事の施工中も、下請業者が許可の範囲内で工事を行っているかを監督する必要があります。
もし、下請業者が無許可営業を行っていることが判明した場合は、元請業者は、直ちに工事を中止させ、適切な許可を持つ業者に交代させるなどの措置を講じる必要があります。
1-3. 業種判断はすべての建設業者に必須:なぜ軽微な工事でも意識すべきか
建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合に必要となりますが、500万円未満の「軽微な工事」のみを請け負う場合であっても、業種判断の意識は重要です。
なぜなら、将来的に500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合、事前にどの業種の許可が必要かを把握しておくことで、スムーズな許可申請が可能になるからです。
また、軽微な工事であっても、複数の業種にまたがる工事や、専門性の高い工事を行う場合は、どの業種に該当するのかを正確に判断する必要があります。
例えば、内装リフォーム工事では、「内装仕上工事」だけでなく、「建具工事」や「電気工事」など、複数の業種が関係してくることがあります。
このような場合、それぞれの工事の規模や内容に応じて、適切な業種を判断し、必要であればそれぞれの業種の許可を取得しておく必要があります。
さらに、近年、建設業界ではコンプライアンス(法令遵守)の意識が高まっており、軽微な工事であっても、建設業法や関連法令を遵守することが求められています。
業種判断を適切に行うことは、コンプライアンスの観点からも非常に重要です。
2どうやって判断する?建設工事の業種区分
建設工事の業種は、建設業法によって29種類に分類されています。これらの業種は、大きく「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つの一式工事と、27種類の専門工事に分けられます。
では、具体的にどのように建設工事の業種を判断すればよいのでしょうか?
ここでは、国土交通省が示している資料や、判断のステップを解説します。
2-1. 基本は「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
建設工事の業種判断の基本的な資料となるのが、国土交通省のホームページに掲載されている「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」です。
この資料は、建設業許可事務ガイドラインの一部として公開されており、建設業許可事務を取り扱う上で重要な指針となっています。
この資料には、29種類の建設工事の業種ごとに、以下の情報が詳細に記載されています。
(1)建設工事の内容(告示):
建設業法に基づく告示(建設業許可に関する基準)で、各業種の定義が示されています。これは、法律上の定義であり、業種判断の最も基本的な根拠となります。
(2)建設工事の例示(建設業許可事務ガイドライン):
各業種に該当する具体的な工事の例が、多数示されています。
これにより、自社が行う工事がどの業種に該当するかのイメージをつかむことができます。
例えば、「塗装工事」であれば、「外壁塗装工事」「屋根塗装工事」「橋梁塗装工事」など、具体的な工事名が列挙されています。
(3)建設工事の区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン):
複数の業種にまたがる工事や、判断が難しい工事について、どの業種に該当するかの考え方が示されています。
例えば、「○○工事と○○工事は、原則として○○工事に該当する」といった形で、判断の基準が示されています。
これらの情報を総合的に参照することで、自社が行う工事がどの業種に該当するかを、客観的に判断することができます。
2-2. 業種判断の3ステップ:実践的な手順
国土交通省の資料を参考に、当事務所では、以下の3つのステップで業種判断を行うことを推奨しています。
この手順に従うことで、よりスムーズかつ正確に業種判断を行うことができます。
2-2-1. 第1段階:
「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」で確認:まずは基本資料にあたる
まずは、基本となる国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」を参照し、請け負う工事がどの業種に該当するかを確認します。
この資料に記載されている「建設工事の内容」「建設工事の例示」をよく読み、自社の工事内容と照らし合わせます。
この資料で明確に判断できる場合は、業種判断は完了です。
この段階で重要なのは、資料に記載されている文言を正確に理解することです。
例えば、「○○工事」と記載されている場合、その工事の範囲や内容を具体的にイメージできる必要があります。
2-2-2. 第2段階:
<複数の業種が含まれる場合の判断:主従関係の見極めがカギ>
1件の工事に複数の業種が含まれる場合は、以下の2つのパターンに分けて考えます。
この段階では、「主たる工事」と「付帯工事」という考え方が重要になります。
(1)主従の関係が明らかな場合:
例えば、建物の外壁塗装工事を行う際に、足場の設置や、ひび割れの補修(左官工事)を行う場合などです。
この場合は、主たる工事である「塗装工事」の許可があれば、付随する工事(とび・土工・コンクリート工事、左官工事)の許可は不要です。
つまり、付帯工事は、主たる工事の許可の範囲内で施工できると解釈されます。
「付帯工事」とは、主たる工事を施工するために必要不可欠な工事、または、主たる工事に付随して行われる工事のことです。
(2)主従の関係が明らかでない場合:
例えば、内装リフォーム工事で、「内装仕上工事」と「建具工事」の両方が含まれる場合などです。
この場合は、それぞれの工事の規模や専門性、工事の目的などを総合的に考慮し、どちらの工事が主たる工事かを判断します。
例えば、壁紙の張り替えがメインで、建具の交換は一部であれば、「内装仕上工事」が主たる工事と判断できます。
それでも判断が難しい場合は、次の第3段階に進みます。
2-2-3. 第3段階:
<「一式工事」に該当するかどうかの判断>
第1段階、第2段階で業種判断ができない場合は、「一式工事」に該当するかどうかを検討します。
(1)一式工事とは:
総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物または建築物を建設する工事のことです。
具体的には、橋梁建設工事やダム建設工事(土木一式工事)、住宅の新築工事や大規模なリフォーム工事(建築一式工事)などが該当します。
一式工事は、原則として、元請業者が請け負う大規模かつ複雑な工事が該当します。
(2)注意点:
下請業者が一式工事を請け負うことは、原則としてできません。
下請工事の場合は、専門工事(一式工事以外の27業種)に該当するはずです。
専門工事に該当する場合は、一式工事ではなく、それぞれの専門工事の許可が必要です。例えば、建物の外壁塗装工事は、「塗装工事」という専門工事に該当するため、「建築一式工事」の許可では請け負うことができません。
2-3. それでも判断できない場合は?:専門家への相談が確実
上記の方法でも業種判断が難しい場合は、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に直接確認するか、建設業許可を専門とする行政書士に相談することをおすすめします。
許可行政庁への確認は、確実な判断を得られる方法ですが、担当者によっては、回答に時間がかかる場合や、明確な回答が得られない場合もあります。
一方、行政書士は、建設業許可に関する専門的な知識や経験を持っており、スムーズな業種判断をサポートしてくれます。
また、許可申請の手続きについても、併せて相談することができます。
3具体例で確認!業種判断のケーススタディ:よくある事例を徹底解説
ここでは、具体的な工事の例を挙げて、業種判断の考え方を確認してみましょう。これらのケーススタディを参考にすることで、より実践的な業種判断の感覚を養うことができます。
3-1. ケース1:外壁の塗り替え工事:シンプルなケース
・工事内容: 建物の外壁の塗り替え工事
・判断: 「塗装工事」に該当します。これは、国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」の「塗装工事」の例示に、「外壁塗装工事」と明記されているため、比較的容易に判断できます。
3-2. ケース2:外壁の塗り替え工事(足場設置、ひび割れ補修あり):付帯工事を含むケース
・工事内容: 建物の外壁の塗り替え工事(足場の設置、ひび割れの補修を含む)
・判断: 主たる工事は「塗装工事」であり、足場の設置は「とび・土工・コンクリート工事」、ひび割れの補修は「左官工事」に該当しますが、これらは「塗装工事」の付帯工事とみなされるため、「塗装工事」の許可があれば工事を請け負うことができます。
・付帯工事と判断する理由:
足場の設置は、外壁塗装工事を行うために必要不可欠な工事である。
ひび割れの補修は、外壁塗装工事の品質を確保するために必要な工事である。
これらの工事は、外壁塗装工事に比べて工事の規模が小さい。
3-3. ケース3:内装リフォーム工事(壁紙の張り替え、建具の交換):複数の専門工事が含まれるケース
・工事内容: 内装リフォーム工事(壁紙の張り替え、建具の交換)
・判断: 壁紙の張り替えは「内装仕上工事」、建具の交換は「建具工事」に該当します。
どちらの工事が主たる工事かを判断し、主たる工事の許可が必要です。
・主たる工事の判断基準:
-工事の規模(金額、面積など)
-工事の専門性
-工事の目的
例えば、壁紙の張り替えがメインで、建具の交換は一部であれば、「内装仕上工事」が主たる工事と判断できます。
両方の工事の規模が同程度で、主従の判断が難しい場合は、両方の許可を取得するか、許可行政庁に確認することをおすすめします。
3-4. ケース4:太陽光発電設備の設置工事:判断が分かれるケース
・工事内容: 太陽光発電設備の設置工事
・判断:
太陽光パネルを設置する工事は、設置場所や方法によって、「屋根工事」または「電気工事」に該当します。
架台の設置は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当することがあります。
土地を造成して太陽光発電設備を設置する場合は、「土木一式工事」に該当することがあります。
建物の屋根に太陽光パネルを設置する場合は、基本的には「屋根工事」に該当しますが、太陽光パネル自体が屋根材としての機能を持つ場合(一体型)は「屋根工事」に、屋根材の上に設置する場合(設置型)は「電気工事」に分類される傾向があります。
このように、太陽光発電設備の設置工事は、複数の業種にまたがる可能性があり、判断が難しいケースの一つです。
事前に許可行政庁や専門家に相談することをおすすめします。
3-5. ケース5:道路の維持・修繕工事:比較的シンプルなケース
・工事内容: 道路の維持・修繕工事
・判断: 基本的に「舗装工事」に該当します。
道路の舗装、補修、維持作業(路面の清掃、除雪など)が含まれます。
ガードレールの設置や道路標識の設置など、付帯する工事があっても、「舗装工事」の許可で対応できるケースが多いです。
これらのケーススタディはあくまで一例です。実際の工事内容は多岐にわたるため、個別の判断が必要になる場合があります。
4業種判断を間違えるとどうなる?:違反のリスクと影響
業種判断を誤り、許可を受けていない業種の工事を請け負ってしまうと、建設業法違反となり、以下のような重大なリスクがあります。
4-1. 罰則:懲役または罰金
建設業法では、無許可営業を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科せられます(建設業法第47条)。
これは、建設業許可制度が、工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するための重要な制度であるため、違反行為に対しては厳しい罰則が設けられているのです。
4-2. 行政処分:指示、営業停止、許可取消
罰則に加えて、行政処分を受ける可能性もあります。
行政処分の内容は、違反の程度や状況によって異なりますが、指示処分、営業停止処分、許可の取消しなどがあります(建設業法第28条、第29条)。
・指示処分: 違反行為の是正や再発防止策の実施などを指示される処分です。
・営業停止処分: 一定期間、建設業を営むことができなくなる処分です。
・許可の取消し: 建設業許可が取り消される処分です。許可が取り消されると、その後5年間は新たな許可を取得できなくなります。
これらの行政処分は、建設業者の事業活動に大きな影響を与えるだけでなく、企業の信用を著しく失墜させる可能性があります。
4-3. その他の影響:入札参加資格喪失、信用失墜、損害賠償
建設業法違反は、罰則や行政処分だけでなく、以下のような様々な影響を及ぼします。
・入札参加資格の喪失:
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が必要であり、かつ、入札参加資格審査を受ける必要があります。建設業法違反があると、この入札参加資格を喪失する可能性があります。
・社会的信用の失墜:
建設業法違反は、企業の社会的信用を大きく損ないます。取引先や金融機関からの信頼を失い、今後の事業活動に支障をきたす可能性があります。
損害賠償請求: 建設業法違反によって発注者や第三者に損害を与えた場合、損害賠償を請求される可能性があります。
これらの影響を総合的に考えると、業種判断の誤りは、建設業者にとって非常に大きなリスクをもたらすことがわかります。
したがって、業種判断は慎重に行い、不明な点があれば、必ず専門家や許可行政庁に相談するようにしましょう。
5業種判断で失敗しないための対策
業種判断で失敗しないためには、以下の対策を講じることが重要です。
5-1. 社内ルールの整備
業種判断の基準や手順を明確化し、社内ルールとして整備する。
判断に迷う場合の相談窓口を設ける。
従業員への教育・研修を実施する。
5-2. 専門家への相談
業種判断に迷う場合は、行政書士などの専門家に相談する。
許可行政庁に直接確認する。
5-3. 最新情報の収集
建設業法や関連法令、ガイドラインなどの改正情報を常にチェックする。
国土交通省や都道府県のホームページなどで、最新の情報を収集する。
6まとめ
建設業許可における「工事の種類(業種)」の判断は、建設業を営む上で非常に重要なプロセスです。
誤った業種判断は、建設業法違反となり、罰則や行政処分を受けるリスクがあります。
今回解説した業種判断のステップや注意点、具体例を参考に、自社の工事に必要な許可業種を正しく判断し、適切な許可を取得・更新しましょう。
「自社の工事はどの業種に該当する?」「複数の業種が含まれる場合はどうすれば?」など、業種判断に関する疑問や不安があれば、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>



.jpg)