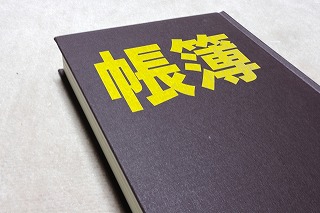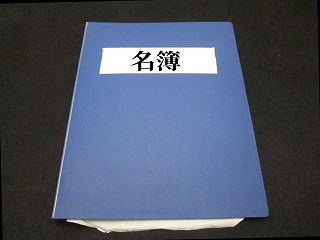「施工体制台帳を作成する義務があるのは分かったけれど、具体的に何を書けばいいの?」
「下請の情報は、どこまで詳しく記載する必要がある?」
「添付しなければならない書類は何?」
元請として、こんな疑問や不安を感じていませんか?
ご安心ください。
その悩みは、建設業法施行規則に定められた記載事項と、添付書類のルールを正しく理解することで解決できます。
この記事では、元請負人の重要な責務である施工体制台帳について、その具体的な記載内容と、絶対に漏らせない添付書類の種類を分かりやすく解説します。
建設工事の現場における複雑な下請関係を明確にし、すべての関係者が適正な施工体制を共有するための重要なツールが「施工体制台帳」です。
前回の記事では、この台帳の作成が「いつ」必要になるのかを解説しましたが、今回はその「中身」、つまり「何を」「どのように」記載しなければならないのかという、より実践的な側面に焦点を当てていきます。
施工体制台帳の作成は、単に書類を一つ作るという作業ではありません。
それは、元請負人として、現場の隅々まで責任を持つという意思表示そのものです。
記載事項の漏れや不備は、企業のコンプライアンス意識を問われる重大な問題に繋がりかねません。
今回は、完璧な施工体制台帳を作成するためのポイントを詳しく見ていきましょう。
1施工体制台帳に記載すべき5つの大項目
施工体制台帳に記載すべき内容は、建設業法施行規則第14条の2で詳細に定められています。
膨大な情報ですが、大きく分けて以下の5つのカテゴリーで整理すると、その全体像が掴みやすくなります。
1-1. ①作成建設業者(元請負人)に関する基本情報
まず、この台帳を作成する元請負人自身の情報を記載します。
⑴ 許可に関する情報:
自社の建設業許可番号や、許可年月日などを正確に記載します。
⑵ 保険加入状況:
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を明記します。
1-2. ②請け負った建設工事に関する情報
次に、今回の工事そのものに関する情報を記載します。
⑴ 工事の特定情報:
工事の名称、工事内容、工期、発注者の商号や住所などを記載します。
⑵ 契約情報:
発注者と締結した請負契約の契約年月日や契約金額を記載します。
⑶ 関係者の情報:
発注者が置く監督員の氏名と権限、自社が置く現場代理人の氏名と権限などを記載します。
1-3. ③元請負人が配置する技術者に関する情報
自社が現場に配置する主任技術者または監理技術者について、その氏名、保有資格、そしてその工事に「専任」で配置されるか否かを明記します。
1-4. ④下請負人に関する情報(すべての下請負人分)
ここが最も重要な部分です。
自社が契約した一次下請負人はもちろんのこと、その先の二次、三次…と、その工事に携わる「すべての」下請負人について、以下の情報を網羅的に記載する必要があります。
⑴ 会社情報:
各下請負人の商号、住所、建設業許可番号などを記載します。
⑵ 契約情報:
各下請負人が担当する工事の内容、工期、契約年月日などを記載します。
⑶ 配置技術者情報:
各下請負人が配置する主任技術者の氏名、保有資格などを記載します。
⑷ 保険加入状況:
各下請負人の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を明記します。
1-5. ⑤外国人材の従事に関する情報
近年の法改正で、外国人材の就労環境を適正に管理する観点から、現場に従事する外国人建設就労者や外国人技能実習生の有無、そしてその具体的な情報を記載することが求められるようになりました。
2台帳の信頼性を担保する「添付書類」
施工体制台帳は、記載するだけでなく、その内容が事実であることを証明するための「添付書類」をセットで保管・管理する必要があります。
これらの書類は、元請負人が用意するものと、下請負人から提出してもらうものがあります。
2-1. 契約関係を証明する書類
① 発注者と元請負人との間の工事請負契約書の写し
② 元請負人と、すべての下請負人との間の下請負契約書の写し(注文書・請書の写しを含む)
2-2. 技術者の資格・雇用関係を証明する書類
③ 元請負人が配置する監理技術者の資格を証明する書面(監理技術者資格者証の写し)
④ 監理技術者補佐を置く場合は、その資格を証明する書面
⑤ 専門技術者を置く場合は、その資格を証明する書面
⑥ 配置技術者と、その所属建設業者との雇用関係を証明する書面(健康保険被保険者証の写しなど)
3国土交通省の「チェックリスト」を活用
これだけ多くの記載事項や添付書類があると、「どこかに漏れがないか不安だ」と感じるのも当然です。
そんな時に非常に役立つのが、国土交通省が公開している「施工体制台帳等のチェックリスト」です。
このチェックリストは、主に公共工事を念頭に作成されていますが、民間工事においても、法令が求める要件を網羅しているかを確認するための、完璧なツールとなります。
国土交通省のウェブサイトからダウンロードできますので、台帳作成の際には、この公式チェックリストを活用し、セルフチェックを行うことを強くお勧めします。
4整理
施工体制台帳を正確に作成し、適切に管理・運用することは、元請負人にとって、単なる事務作業ではありません。
それは、複雑なプロジェクト全体を俯瞰し、関わるすべての企業を一つのチームとしてまとめ上げ、工事を成功に導くための「統率力」そのものの証です。
この台帳を通じて、自社の施工体制が法令を遵守した、透明性の高いものであることを発注者や社会に示すことが、企業の信頼性を高め、次のビジネスチャンスを掴むための礎となるのです。
5まとめ
施工体制台帳の作成は、特定建設業者や公共工事の元請負人に課せられた、建設業法上の重要な義務です。
その記載事項は多岐にわたり、一つでも不備があれば、企業のコンプライアンス体制を問われかねません。
「自社の台帳の作り方は、これで本当に正しいのか」「下請から、どのような書類を、どのタイミングで集めれば良いのか」など、具体的な作成・運用でお悩みでしたら、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、最新の法令や行政の指導に基づいた、完璧な施工体制台帳の作成をサポートします。
貴社の健全な事業運営を、法務面から力強く支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/

.jpg)