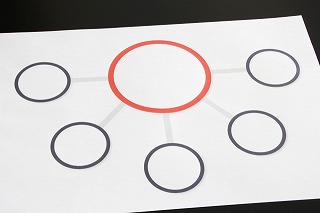「若手社員にもっと早く施工管理技士の資格を取らせたい…」
「技術検定の受検資格が変わったと聞いたけれど、具体的にどうなったの?」
「実務経験の数え方が複雑で、自社の社員が受験できるか分からない」
こんなお悩みはありませんか?
ご安心ください。
その疑問は、2024年度(令和6年度)から大きく変わった「施工技術検定」の新しい受検資格を正しく理解することで解決できます。
この記事では、建設業界の未来を担う若手技術者のための、新しい技術検定のルールと、それを活用するためのポイントについて、分かりやすく解説します。
建設業界が直面する深刻な担い手不足。この課題を克服し、未来の建設産業を支える優秀な技術者を一人でも多く、そして一日でも早く育成するため、建設業の根幹をなす国家資格「施工管理技士」への道が、2024年度(令和6年度)から大きく開かれました。
これまで、若手技術者の前に立ちはだかっていた「実務経験」という高い壁が、大幅に見直されたのです。
この制度変更は、企業の技術者育成戦略を根本から変える可能性を秘めた、非常に重要な改革です。
今回は、この新しいルールについて、その核心を詳しく見ていきましょう。
1技術検定の基本
まず、技術検定制度の基本的な仕組みをおさらいしましょう。
1-1. 技術者の能力を証明する国家資格
技術検定とは、建設工事に従事する技術者のスキルアップを目的とした国家試験制度です。
この検定に合格することで、建設業法が定める営業所技術者や、工事現場に配置が義務付けられている主任技術者・監理技術者といった、建設業許可に不可欠な技術者として認められることになります。
1-2. 7つの専門分野
技術検定は、以下の7つの種目に分かれており、それぞれに1級と2級があります。
① 土木施工管理
② 建築施工管理
③ 電気工事施工管理
④ 管工事施工管理
⑤ 造園施工管理
⑥ 建設機械施工管理
⑦ 電気通信工事施工管理
1-3. 「技士」と「技士補」の称号
技術検定は、知識を問う「第1次検定」と、実務能力を問う「第2次検定」で構成されています。
① 第1次検定合格者:
「技士補(ぎしほ)」の称号を得られます。監理技術者の補佐役などとして活躍できます。
② 第2次検定合格者:
「技士(ぎし)」の称号を得られ、主任技術者や監理技術者(1級の場合)になることができます。
2【最重要】2024年度からの受検資格の大きな変更点
今回の制度改正の最大のポイントは、この第1次検定と第2次検定の受検資格が、それぞれ大きく見直された点です。
2-1. 変更点①:第1次検定は、実務経験が「不要」に!
これまで、第1次検定の受検にも一定の実務経験が必要でした。
しかし、この要件が完全に撤廃され、試験実施年度における年齢が満19歳以上(1級)または満17歳以上(2級)であれば、誰でも受検できるようになりました。
これにより、例えば工業高校の学生が在学中に2級の第1次検定に挑戦したり、大学で建築を学ぶ学生が、卒業を待たずに1級の第1次検定に合格したり、といった早期の資格取得が可能になります。
2-2. 変更点②:第2次検定の「実務経験」要件の合理化
第2次検定の受検には、引き続き実務経験が必要ですが、そのカウント方法が合理化されました。
基本的には、「第1次検定合格後の実務経験」が評価される形となり、より実態に即した能力評価へとシフトしています。
(例:1級の場合、第1次検定合格後、指導監督的な実務経験1年以上、または実務経験3年以上などで受検可能)
3認められる「実務経験」とは?
第2次検定の受検や、10年以上の実務経験で主任技術者を目指す際に、その「実務経験」の内容は厳しく審査されます。
建築施工管理技術検定を例に、認められる経験と認められない経験の具体例を見ていきましょう。
3-1. 認められる工事の種類と経験内容
① 対象工事:
建設工事29業種のうち、建築一式工事、大工工事、内装仕上工事など、定められた17種類の工事に関する経験が対象となります。
② 経験内容:
実際に工事現場で、施工管理(工程・品質・安全管理など)、施工監督、設計監理といった、技術上の管理に関わった経験が求められます。
3-2. 実務経験として「認められない」6つのケース
一方で、以下のような業務は、原則として実務経験には含まれませんので、注意が必要です。
① 保守、点検、メンテナンス、清掃、調査などの業務
② 建設工事の現場における、単なる雑務や事務作業のみ
③ アルバイトや派遣社員としての業務経験
④ 設計業務のみ(設計監理は除く)
⑤ 入社後の社内研修や、教育訓練施設での研修期間
⑥ 海外での工事経験(日本の建設業法に基づく経験が対象) 等
4整理
今回の技術検定の受検資格緩和は、建設業界の未来を担う若手人材にとって、キャリアアップへの道を大きく拓くものです。
そして、企業にとっては、若手社員の育成計画を前倒しで進め、より早期に有資格者を確保し、経営事項審査(経審)での評価を高め、受注機会を拡大するための絶好の機会と言えます。
この新しいルールをいち早く理解し、自社の育成プログラムや採用戦略に組み込んでいくこと。
それが、これからの人手不足時代を勝ち抜き、企業の「無限の可能性」を広げていくための、賢明な経営判断となるでしょう。
5まとめ
2024年度から始まった技術検定の受検資格緩和は、建設業者の皆様にとって、若手技術者を育成し、企業の技術力を強化する大きなチャンスです。
しかし、その一方で、実務経験の証明など、手続きは依然として専門的な判断を要します。
「自社の若手社員が、新しい制度でいつ受験できるのか知りたい」「実務経験証明書の作成方法が分からない」といったお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令に基づき、貴社の技術者育成と、それに伴う建設業許可・経審の戦略をトータルでサポートします。
元岩手県職員としての経験も活かし、貴社の事業運営を力強く支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/