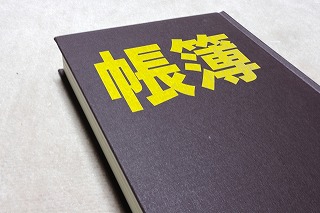「『施工体制台帳』って、そもそも何のために作るの?」「今回の工事で、施工体制台帳の作成は義務付けられているだろうか?」
「施工体系図との違いがよく分からない…」こんな疑問や不安を感じたことはありませんか?
ご安心ください。
その疑問は、建設業法が定める元請負人の重要な責務、「施工体制台帳」の作成ルールを正しく理解することで解決できます。
この記事では、すべての元請負人が知っておくべき施工体制台帳の目的と、作成が義務付けられる具体的なケース、そしてその記載内容までを分かりやすく解説します。
建設工事の現場では、元請負人を頂点として、数多くの専門工事業者が下請として関わる、複雑なピラミッド構造が形成されます。
この構造を明確に「見える化」し、工事全体の適正な施工体制を確保するために、元請負人に作成が義務付けられている極めて重要な書類が「施工体制台帳」です。
この書類は、単なる事務手続きのためのものではありません。
それは、元請負人が現場のすべてを把握し、責任を果たすための「羅針盤」であり、企業のコンプライアンス意識を内外に示す重要な証となります。
今回は、この施工体制台帳について、その本質から具体的な作成ルールまで詳しく見ていきましょう。
1プロジェクトの「カルテ」
まず、なぜ法律は元請負人に対して、施工体制台帳の作成を義務付けているのでしょうか。
その背景には、建設生産システムの透明性を高め、様々なリスクを未然に防ぐための、3つの大きな目的があります。
1-1. 目的①:施工体制の正確な把握とトラブル防止
施工体制台帳には、その工事に関わるすべての下請負人の情報(会社名、許可番号、担当する工事内容、配置技術者など)が網羅的に記載されます。
これにより、元請負人は、自社の目の届きにくい二次、三次下請に至るまで、誰が、どこで、どのような工事を行っているのかを正確に把握することができます。
この正確な把握が、品質、工程、安全管理上のトラブルを未然に防ぐための第一歩となります。
1-2. 目的②:不良・不適格業者の排除
建設業許可を持たない業者に500万円以上の工事を下請けさせることや、工事を丸投げする「一括下請負」は、建設業法で固く禁じられています。
施工体制台帳を作成し、各社の許可情報を明記するプロセスは、こうした法令違反行為を防ぎ、施工能力のない不良・不適格業者が現場に参入することを排除する、重要なフィルターの役割を果たします。
1-3. 目的③:安易な重層下請構造の抑制
下請が何重にも重なる「重層下請構造」は、中間搾取を生み、末端の作業員の賃金低下や、責任の所在の曖昧化を招くなど、多くの問題点が指摘されています。
施工体制を「見える化」することは、こうした安易な重層化に歯止めをかけ、建設生産システムの効率化と合理化を促す目的も担っています。
2作成義務が発生する2つのケース
施工体制台帳は、すべての工事で作成が義務付けられているわけではありません。
その義務が発生するのは、主に以下の2つのケースです。
2-1. ケース①:大規模な下請契約を伴う民間工事
特定建設業者である元請負人が、発注者から直接請け負った民間工事において、その工事のために締結した下請契約の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合、施工体制台帳の作成が義務付けられます。
※この金額は2023年(令和5年)1月1日からの改正後の金額です。
ポイントは、「元請負人が特定建設業者であること」と、「下請契約の『総額』」で判断される点です。
2-2. ケース②:公共工事
国や地方公共団体などが発注する公共工事の場合は、下請契約の金額にかかわらず、元請負人は必ず施工体制台帳を作成しなければなりません。
これは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」によって定められています。
さらに、公共工事の場合は、作成した施工体制台帳の写しを、発注者に提出する義務もあります。
3一目でわかる「施工体系図」の役割
施工体制台帳とセットで作成が義務付けられているのが「施工体系図」です。
3-1. 施工体制を「見える化」するチャート
施工体系図とは、施工体制台帳に記載された各下請負人の関係性を、系統図(組織図のようなもの)として一枚の図面にまとめたものです。
これにより、元請負人を頂点とした、各下請負人間の施工の分担関係が一目で分かるようになります。
3-2. 現場への掲示義務
作成した施工体系図は、工事現場の見やすい場所(例:公衆が見やすい場所、工事関係者が見やすい場所)に掲示することが義務付けられています。
これにより、工事に関わるすべての人が施工体制を共有し、透明性の高い現場運営を実現します。
4整理
施工体制台帳と施工体系図の作成・整備は、法律で定められた元請負人の重要な責務です。
これらの書類を適切に作成し、活用することは、単に法令を遵守するというだけでなく、元請負人として工事全体の品質・安全・工程に責任を持つという、強い意志の表れでもあります。
下請負人との間で、明確で透明性の高い施工体制を共有することは、健全なパートナーシップを築き、プロジェクトを成功に導くための不可欠なプロセスです。
自社の管理体制が、法律の求める基準を満たしているか、この機会にぜひ一度、丁寧にご確認ください。
5まとめ
施工体制台帳の作成と活用は、元請負人にとって、建設業法が定める最も基本的な責務の一つです。
特に公共工事や、特定建設業者として大規模な工事を手掛ける際には、その作成が絶対的な義務となります。
この義務を怠ると、監督処分の対象となるだけでなく、発注者や社会からの信頼を失うことにも繋がりかねません。
「自社のこの工事では、台帳は必要なのか」「記載すべき内容がよく分からない」など、お悩みは専門家にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令に基づき、適正な施工体制台帳の作成から、コンプライアンス体制の構築までをサポートします。
元岩手県職員としての経験も活かし、貴社の健全な事業運営を力強く支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/

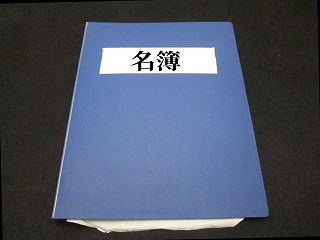
.jpg)