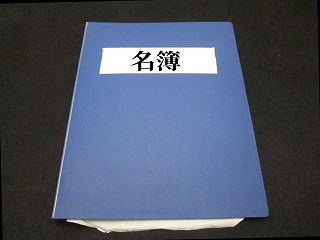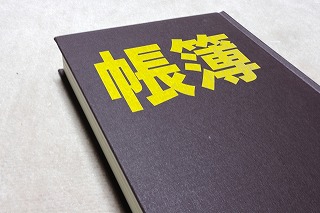
「工事現場に出入りする業者はたくさんいるが、一体どこまでを施工体制台帳に記載すれば良いのだろう?」
「単に資材を納入するだけの業者や、交通整理の警備会社も、下請負人として記載する必要があるのか?」
こんな疑問を感じていませんか?
ご安心ください。
その悩みは、施工体制台帳の記載対象となる「下請負人」の定義を正しく理解することで解決できます。
この記事では、元請負人の皆様が判断に迷いやすい、施工体制台帳への記載が必要な業者と、そうでない業者の明確な線引きについて、分かりやすく解説します。
元請負人の重要な責務の一つである「施工体制台帳」の作成。
これは、工事に関わるすべての下請負人をリストアップし、プロジェクト全体の施工体制を「見える化」するための、建設業コンプライアンスの根幹をなす書類です。
しかし、実際の現場では、建設工事を直接行う下請負人以外にも、資材を納入する業者、産業廃棄物を運搬する業者、現場の安全を守る警備会社など、非常に多くの事業者が関わります。
「これらの関連業者も、すべて台帳に記載しなければならないのか?」これは、多くの元請負人様が頭を悩ませる問題です。
今回は、この記載対象の範囲について、その明確な判断基準を詳しく見ていきましょう。
1すべての判断の基礎となる「建設工事の請負契約」
まず、施工体制台帳の記載対象を判断するための、最も重要な大原則を理解することが不可欠です。
それは、「施工体制台帳に記載するのは、『建設工事の請負契約』を締結した下請負人に限られる」ということです。
建設業法第24条の8では、施工体制台帳は「その建設工事を請け負わせた建設業者(=下請負人)」について作成するものと定めています。
つまり、契約の目的が「建設工事の完成」ではない場合、その契約相手は、原則として施工体制台帳への記載対象とはなりません。
2原則として「記載不要」となるケース
この大原則に基づくと、以下のような契約を結んだ相手方は、たとえ現場に出入りしていたとしても、通常は施工体制台帳への記載は不要です。
2-1. 資材の納入業者
単にセメントや鋼材といった建設資材を現場に納入するだけの契約は、「物品の売買契約」であり、「建設工事の請負契約」ではありません。
したがって、資材業者を台帳に記載する必要はありません。
【要注意ポイント】
ただし、その資材業者が、納入だけでなく、現場での「据付・取付・設置」といった工事までを請け負っている場合は、その設置工事部分が「建設工事の請負契約」に該当するため、台帳への記載が必要となります。
2-2. 建設機械のリース・レンタル業者
クレーンや掘削機などの建設機械を、オペレーターなしでリース・レンタルする契約は、「物品の賃貸借契約」であり、記載は不要です。
2-3. 産業廃棄物の収集運搬業者
現場で発生した産業廃棄物の収集と運搬のみを委託する契約も、建設工事には該当しないため、記載は不要です。
(※別途、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の管理は当然必要です。)
2-4. 警備会社・測量会社など
工事現場の交通誘導警備や、事前の地質調査、測量業務などは、それぞれ「警備業務委託契約」や「調査業務委託契約」であり、建設工事ではないため、原則として記載は不要です。
3間違いやすい!必ず「記載が必要」となるケース
一方で、以下のようなケースは、たとえ元請負人様の頭の中に「下請負人」という意識が薄くとも、法律上は明確に記載が義務付けられています。
3-1. すべての階層の下請負人
元請負人が直接契約した一次下請負人はもちろんのこと、その先の二次、三次、四次…と、その工事に関わるすべての階層の下請負人が記載対象です。
元請負人には、自社が直接契約していない下位の下請負人についても、その情報を把握し、台帳に記載する責任があります。
3-2. 建設業許可のない下請負人
これが、最も誤解が多く、注意が必要なポイントです。
下請負人が請け負った工事が、500万円未満の「軽微な建設工事」であり、その下請負人が建設業許可を持っていなかったとします。
しかし、契約内容が「建設工事の請負契約」であることに変わりはありません。
したがって、たとえ建設業許可のない事業者であっても、建設工事を下請けしている以上は、施工体制台帳への記載が「必要」です。
「無許可業者だから書かなくて良い」という考えは、明確な誤りです。
4公共工事における特別なルール
民間工事では記載不要とされる警備会社なども、公共工事においては、施工体制台帳への記載を求められる場合があります。
これは、建設業法そのものの規定というよりは、発注機関(国や地方公共団体など)ごとの、独自の運用ルールや特記仕様書によって定められているものです。
例えば、国土交通省の直轄工事では、「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」などに基づき、一次下請負人となる警備会社や測量会社などについても、その会社名や現場責任者などを台帳に記載するよう求められることがあります。
公共工事を請け負う際には、契約書や仕様書を細部まで確認し、発注者が求める記載範囲を正確に把握することが不可欠です。
5整理
施工体制台帳は、元請負人が現場全体の責任者として、その施工体制を完全に把握・管理していることを示すための重要な証拠書類です。
誰を記載し、誰を記載しないのか。その判断基準は、ただ一つ「その契約は、建設工事の完成を目的とする請負契約か?」という点に尽きます。
この原則と、公共工事などにおける例外ルールを正しく理解し、抜け漏れのない施工体制台帳を作成すること。
それこそが、元請負人としての重い責任を果たし、発注者からの信頼を勝ち得るための、最も重要な第一歩と言えるでしょう。
6まとめ
施工体制台帳の記載対象を正しく判断することは、元請負人にとって重要なコンプライアンス課題です。
「建設工事の請負契約」に該当しない資材業者などは原則記載不要ですが、「無許可の下請負人」は記載が必要であるなど、そのルールは複雑です。
「この業者は、台帳に記載すべきか?」「公共工事の特別なルールが分からない」など、施工体制台帳の作成でお悩みでしたら、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、最新の法令や行政の指導に基づいた、完璧な施工体制台帳の作成をサポートします。
貴社の健全な事業運営を、法務面から力強く支援いたします。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/





.jpg)