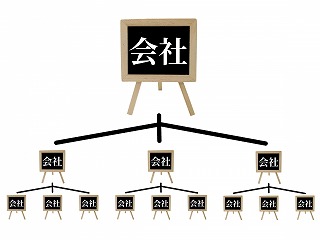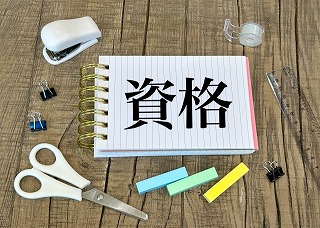「深刻な人手不足、派遣社員に現場作業を手伝ってもらうことはできないだろうか?」
「現場事務所の事務員なら、派遣でも問題ないと聞いたが本当?」
「現場監督や施工管理業務への派遣は、法律的にどうなの?」
こんな疑問を感じていませんか?
ご安心ください。
その疑問は、労働者派遣法が定める「建設業務」への派遣禁止ルールを正しく理解することで、明確に解決できます。
この記事では、なぜ建設現場への労働者派遣が禁止されているのか、その理由と、例外的に派遣が認められる業務との境界線について、分かりやすく解説します。
深刻な人手不足は、建設業界が抱える最も大きな経営課題の一つです。
急な欠員や、繁忙期の人員補充のために、「労働者派遣サービスを利用したい」と考える経営者様も多いことでしょう。
しかし、ここで絶対に知っておかなければならないのが、建設現場における作業への労働者派遣は、労働者派遣法によって原則として固く禁止されているという事実です。
このルールを知らずに安易に派遣労働者を現場に受け入れてしまうと、意図せず法令違反となり、厳しい罰則の対象となる可能性があります。
今回は、企業のコンプライアンスを守るため、この「建設業務への労働者派遣の禁止」について、その本質と具体的な判断基準を詳しく見ていきましょう。
1なぜ建設業務への労働者派遣は禁止されているのか?
労働者派遣法第4条では、いくつかの業務について労働者派遣事業を行うことを禁止しており、その筆頭に挙げられているのが「建設業務」です。
なぜ、他の多くの業種で認められている労働者派遣が、建設業務ではこれほど厳しく規制されているのでしょうか。
その背景には、建設現場の特殊性と、労働者を守るための3つの重要な理由があります。
1-1. 理由①:安全管理上の指揮命令系統を明確にするため
建設現場は、重機が稼働し、高所での作業も伴う、常に危険と隣り合わせの場所です。
安全を確保するためには、元請負人を中心とした、明確で、階層の少ない、直接的な指揮命令系統が不可欠です。
ここに派遣会社が介在し、「雇用主(派遣元)」と「指揮命令者(派遣先)」が分離すると、安全に関する指示や責任の所在が曖昧になり、万が一の事故の際に、迅速で的確な対応が困難になる恐れがあります。
1-2. 理由②:工事の完成に対する責任を明確にするため
建設工事の請負契約は、仕事の「完成」に対して責任を負うものです。
派遣労働者は、あくまで派遣先の指揮命令の下で労働力を提供するものであり、仕事の完成に対する責任は負いません。
この責任の所在を明確にするためにも、建設業務は、請負契約というピラミッド構造の中で、直接雇用の労働者によって行われるべきであると考えられています。
1-3. 理由③:「偽装請負」を助長させないため
建設業界は、もともと重層的な下請構造が存在します。
ここに労働者派遣が混在すると、請負契約を装いながら、実態は元請が下請の労働者を直接使う「偽装請負」が、より容易に、かつ複雑な形で行われる温床となりかねません。
これを防ぐことも、禁止の大きな理由の一つです。
2禁止される「建設業務」の具体的な範囲
では、法律が禁止している「建設業務」とは、具体的にどこまでの範囲を指すのでしょうか。
この線引きを正しく理解することが、コンプライアンスの鍵となります。
2-1. 禁止の対象は「現場での身体的な作業」
禁止されているのは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の作業に係る業務です。
簡単に言えば、工事現場の「現場」において、直接、身体を動かして行う作業のほぼ全てが該当すると考えてください。
2-2. 例外的に派遣が「可能」な業務
一方で、同じプロジェクトに関わる業務であっても、以下のようなケースは「建設業務」には該当せず、労働者派遣が認められています。
⑴ 現場事務所での事務作業:
電話応対、書類作成、データ入力、CADオペレーターなど、工事現場の敷地内に設けられた事務所内で行われる、身体的な作業を伴わない事務職については、派遣が可能です。
⑵ 現場への搬入・搬出:
運送会社が、資材を現場の所定の場所に降ろすまでの「運搬業務」は、建設業務には当たりません。
3判断に迷うグレーゾーン
ここが最も判断に迷い、注意が必要な点です。
「工事の段取りや管理を行う『現場監督』や『施工管理』の業務なら、直接的な作業ではないから派遣でも良いのでは?」と考えてしまうのは非常に危険です。
3-1. 施工管理業務も「原則禁止」
結論から言うと、施工管理業務(現場監督)への労働者派遣も、建設業務と一体不可分なものとして、原則として禁止されています。
なぜなら、施工管理の職務は、現場を巡回し、作業の進捗を確認し、時には作業員に具体的な指示を出すなど、現場の身体的な作業と密接に関連しているからです。
これを許可してしまうと、前述した指揮命令系統の混乱や責任の所在の曖昧化といった、法律が禁止する趣旨そのものが骨抜きになってしまう可能性があります。
したがって、「現場監督」や「施工管理」といった名目で、安易に派遣労働者を受け入れることは、偽装請負と判断されるリスクが極めて高い行為です。
3-2. 主任技術者・監理技術者は、そもそも派遣の対象外
言うまでもありませんが、建設業法によって「直接的かつ恒常的な雇用関係」が求められる主任技術者・監理技術者を、派遣社員が務めることはできません。
4整理
建設業務への労働者派遣の禁止は、現場の安全と品質、そして労働者の保護を目的とした、建設業界における極めて重要なルールです。
人手不足が深刻な状況だからこそ、安易な解決策に飛びつきたくなる気持ちも理解できます。
しかし、法令違反のリスクを冒してまで派遣労働者を現場作業に従事させることは、企業の信用を失墜させ、かえって経営を危うくする行為に他なりません。
人手不足という課題に対しては、協力会社との連携強化や、若手人材の育成・定着、そしてICTの活用による生産性向上といった、正攻法で、かつ持続可能な方法で向き合っていくことが、これからの建設業者に求められる姿と言えるでしょう。
5まとめ
建設現場への労働者派遣は、労働者派遣法によって原則として禁止されている、非常にリスクの高いコンプライアンス違反です。
「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、厳しい罰則に繋がる可能性もあります。
「自社のこの業務は、派遣で対応できるだろうか」「人手不足を解消するための、適法な方法を知りたい」といったお悩みは、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令に基づき、貴社のコンプライアンス体制構築をサポートします。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、貴社の健全な事業運営を力強く支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/