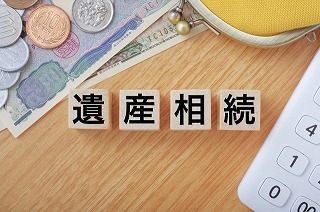「あの人には、絶対に財産を渡したくない…」
「相続人から外したい人がいるけど、どうすればいいの?」
「相続欠格って、どんな場合に認められるの?」
こんな悩みはありませんか?
相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を、誰が、どのように引き継ぐかを決める、重要な手続きです。
しかし、相続人の中に、財産を渡したくない人がいる場合や、相続人にふさわしくない行為をした人がいる場合もあります。
そのような場合に検討されるのが、「相続欠格」と「相続人廃除」という制度です。
ご安心ください!
今回の記事では、「相続欠格」と「相続人廃除」について、その違いや要件、手続きなどを、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、相続に関する疑問や不安が解消され、適切な対応を取ることができます。
特に岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1相続欠格
相続欠格とは、民法で定められた一定の重大な非行があった場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。
相続欠格となる事由(理由)は、民法891条に規定されています。
1-1. 相続欠格事由
以下の5つのいずれかに該当する人は、相続欠格者となり、相続権を失います。
(1)故意に被相続人、または先順位・同順位の相続人を死亡させるに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
亡くなった本人(被相続人)や、自分より先順位または同順位の相続人を、故意に殺害したり、殺害しようとしたりして刑罰を受けた人です。
殺人罪だけでなく、殺人未遂罪、殺人予備罪なども含まれます。
刑に処せられたことが要件であり、逮捕されただけ、起訴されただけでは、相続欠格にはなりません。
・具体例:
-長男が、遺産を独り占めするために、父親を殺害した場合。
-次男が、長男を殺害しようとして未遂に終わり、逮捕・起訴され、有罪判決を受けた場合。
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
亡くなった本人(被相続人)が殺害されたことを知っていながら、それを警察などに告発・告訴しなかった人です。
ただし、その人に是非の弁別がないとき(判断能力がないとき)、または殺害者が自分の配偶者や直系血族(親、子、祖父母、孫など)であったときは、例外的に相続欠格にはなりません。
・具体例:
-夫が殺害されたことを知っていた妻が、犯人隠避のために、警察に届け出なかった場合。
-父親が殺害されたことを知っていたが、犯人が自分の母親であったため、告発しなかった場合(この場合は相続欠格にはならない)。
(3)詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げた者
詐欺(だますこと)や強迫(脅すこと)によって、亡くなった本人(被相続人)が遺言書を作成したり、撤回したり、取り消したり、変更したりすることを妨害した人です。
・具体例:
-長男が、父親に「遺言書を書かなければ、危害を加える」と脅して、遺言書の作成を妨害した場合。
-次男が、父親を騙して、自分に有利な内容の遺言書を書かせようとしたが、途中で父親が気づいて遺言書の作成を中止した場合。
(4)詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または遺言を撤回させ、取り消させ、もしくは変更させた者
詐欺や強迫によって、亡くなった本人(被相続人)に遺言書を作成させたり、撤回・取消・変更させたりした人です。
・具体例:
-長男が、父親に「遺言書を書き換えないと、施設に入れない」と脅して、自分に有利な内容に遺言書を書き換えさせた場合。
-次男が、父親を騙して、遺言書を破棄させた場合。
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿した者
亡くなった本人(被相続人)の遺言書を偽造(勝手に作る)、変造(内容を書き換える)、破棄(捨てる、燃やすなど)、隠匿(隠す)した人です。
・具体例:
-長男が、父親の遺言書を勝手に書き換えた場合。
-次男が、自分に不利な内容の遺言書を破り捨てた場合。
-三男が、遺言書を見つけたが、自分に不利な内容だったので隠した場合。
1-2. 相続欠格の効果
相続欠格に該当する人は、特別な手続きをしなくても、法律上当然に相続権を失います。
家庭裁判所の審判などは必要ありません。
また、相続欠格の効果は、相続開始時にさかのぼって発生します。
つまり、相続欠格者は、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
1-3. 相続欠格と戸籍(記載されない)
相続欠格は、法律上当然に効果が生じるため、戸籍に「相続欠格」と記載されることはありません。
しかし、相続欠格者を除外して相続手続きを進めるためには、相続欠格の事実を証明する必要があります。
例えば、上記の1.のケースであれば、有罪判決の判決謄本などを提出して証明することになります。
1-4. 相続欠格と遺贈
相続欠格者は、相続人になることができないだけでなく、亡くなった本人(被相続人)から遺言によって財産を譲り受けること(遺贈)もできません。
1-5. 相続欠格と代襲相続
相続欠格者がいる場合でも、その人に子がいる場合は、「代襲相続が発生」します。
例えば、長男が父親を殺害して相続欠格者となった場合でも、長男に子(亡くなった本人(被相続人)の孫)がいれば、その孫が代襲相続人になります。
これは、相続欠格が、その人個人のみに帰属する(一身専属)ものであり、その子には影響を及ぼさないと考えられているためです。
相続欠格は、「悪いことをした本人」に対する制裁、と考えるとわかりやすいでしょう。
2相続人の廃除(相続権を奪う制度)
相続人の廃除とは、亡くなった本人(被相続人)の意思に基づいて、家庭裁判所の審判または調停によって、特定の相続人の相続権を奪う制度です。
相続欠格とは異なり、法律上当然に相続権を失うわけではなく、家庭裁判所の手続きが必要となります。
2-1. 廃除の理由
相続人の廃除が認められるのは、以下の2つのいずれかに該当する場合です。
(1)被相続人に対する虐待、重大な侮辱:
亡くなった本人(被相続人)に対して、虐待(暴力を振るう、精神的に傷つけるなど)や、重大な侮辱(名誉を傷つける、人格を否定するなど)をした場合です。
・具体例:
-長年、親に暴力を振るっていた。
-親に対して、公然と侮辱的な発言を繰り返していた。
(2)その他の著しい非行:
上記以外にも、相続人に著しい非行があった場合です。
何が「著しい非行」にあたるかは、個別のケースごとに判断されます。
・具体例:
-親の財産を勝手に使い込んだ。
-ギャンブルで多額の借金を作り、親に返済させた。
-長年、親と音信不通だった。
(判例)父(被相続人)の多額の財産をギャンブルにつぎ込んで減少させ、父が自宅を売却せざるを得ない状況に追い込んだ長男について、廃除が認められた例があります。
2-2. 廃除の対象となる相続人
相続人の廃除は、遺留分を有する相続人(配偶者、子、直系尊属)に対してのみ行うことができます。
兄弟姉妹には遺留分が「ない」ため、廃除の対象とはなりません。
これは、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で「兄弟姉妹には相続させない」と記載すれば、相続させないことが可能であるため、廃除制度を利用する必要がないからです。
2-3. 廃除の手続き
相続人の廃除には、以下の2つの方法があります。
(1)生前廃除:
亡くなった本人(被相続人)が、生前に家庭裁判所に廃除の申立てをする方法です。
(2)遺言廃除:
亡くなった本人(被相続人)が、遺言書で廃除の意思を表示する方法です。
この場合は、遺言執行者が、遺言の効力発生後、家庭裁判所に廃除の申立てをする必要があります。
いずれの場合も、家庭裁判所の審判または調停によって、廃除が認められるかどうかが決まります。
2-4. 廃除の効果(戸籍に記載)
相続人の廃除が認められると、その相続人は相続権を失います。
生前廃除の場合は、家庭裁判所の審判が確定した時点、または調停が成立した時点で、相続権を失います。
遺言廃除の場合は、相続開始時(亡くなった本人(被相続人)の死亡時)にさかのぼって相続権を失います。
廃除されたことは、「戸籍に記載」されます。
2-5. 廃除と代襲相続
相続人の廃除の場合も、相続欠格と同様に、代襲相続は発生します。
例えば、父親が長男を廃除した場合でも、長男に子(亡くなった本人(被相続人)の孫)がいれば、その「孫が代襲相続人」になります。
これは、廃除が、あくまでも「被相続人の意思」に基づくものであり、その効果は、廃除された相続人本人にのみ及び、その子には及ばないと解釈されるからです。
2-6. 廃除の取り消し
相続人の廃除は、亡くなった本人(被相続人)の意思に基づいて行われるため、いつでも取り消すことができます。
(1)生前廃除の場合:
亡くなった本人(被相続人)が、家庭裁判所に廃除の取り消しを請求します。
(2)遺言廃除の場合:
遺言書で廃除を取り消す旨を記載します。
廃除が取り消されると、廃除されていた相続人は、再び相続権を取得します。
3相続欠格・廃除に関する注意点
3-1. 相続欠格・廃除は、慎重に判断する
相続欠格や相続人の廃除は、相続人の権利を奪う重大な効果を持つため、慎重に判断する必要があります。
特に、相続人の廃除は、家庭裁判所の判断が必要となるため、証拠の収集や、法的な主張の組み立てなどが重要になります。
3-2. 相続欠格・廃除と遺留分
相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った人は、遺留分を請求することもできません。
3-3. 相続欠格・廃除と生命保険金
相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った人でも、生命保険金受取人として指定されていれば、生命保険金を受け取ることができます。
生命保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の財産と考えられているためです。
3-4. 相続欠格・廃除と税金
相続欠格や相続人の廃除によって相続人が変わった場合、相続税の計算にも影響が出ることがあります。
相続税の計算は、法定相続人の数や、各相続人の相続分に基づいて行われるためです。
4まとめ
相続欠格と相続人廃除は、どちらも相続人の権利を奪う制度ですが、その要件や手続き、効果は大きく異なります。
相続欠格は、法律上当然に相続権を失う制度であり、相続人廃除は、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所の手続きによって相続権を奪う制度です。
相続欠格や相続人廃除は、相続に関するトラブルの中でも、特に複雑で、感情的な対立が起こりやすい問題です。
「相続欠格に該当するのかどうか、判断が難しい」「相続人廃除の手続きを進めたいが、何から手を付けていいか分からない」など、お困りの場合は、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、法律と手続きの専門家であり、相続に関する様々な問題について、的確なアドバイスとサポートを提供することができます。
特に、相続人廃除は、家庭裁判所への申立てが必要となるため、専門的な知識と経験が不可欠です。
当事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
相続に関するお悩みは、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
相続は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
むしろ、次の世代に向けて、亡くなった方(被相続人)の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要なバトンタッチです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも相続について考えるきっかけになれば幸いです。
5お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ