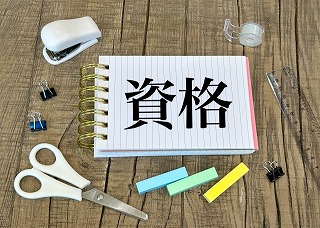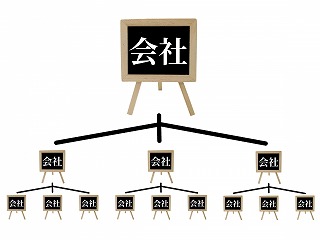「専任で配置した主任技術者が、研修や休暇で数日間、現場を離れることは許されるの?」
「『専任』とは、一日中ずっと現場にいなければならない、という意味なのだろうか…」
こんな疑問から、技術者の休暇取得をためらってはいませんか?
ご安心ください。
その疑問は、建設業法が定める「専任」の本当の意味と、適切な体制づくりのルールを理解することで解決できます。
この記事では、専任技術者が適法に休暇を取得するための具体的な条件や、その際に会社が整備すべき体制について、分かりやすく解説します。
建設工事の現場において、品質と安全の要となる「主任技術者」および「監理技術者」。
一定規模以上の工事では、これらの技術者を「専任」で配置することが建設業法で義務付けられています。
この「専任」という言葉の重みから、「工事期間中は一日も現場を離れられないのではないか」という誤解が、経営者様や技術者様ご自身の大きな負担になっているケースは少なくありません。
しかし、結論から言えば、適切な手順と体制を整えれば、専任技術者も休暇を取得することは可能です。
今回は、建設業界の働き方改革にも繋がる、この重要なルールについて詳しく見ていきましょう。
1大前提:「専任」は「常駐」を意味しない
まず、すべての基本となる考え方として、技術者に求められる「専任」と、「常駐」の違いを理解しておく必要があります。
1-1. 「専任」の本質は「兼務の禁止」
法律が求める「専任」とは、その技術者が他の工事現場の職務と兼務することなく、担当する特定の工事現場の職務に専ら従事することを意味します。
これは、重要な工事に対して、一人の技術者が責任をもって集中できる体制を確保するためのルールです。
1-2. 「常駐」までは求められていない
したがって、「専任」は、必ずしも24時間365日、工事現場に物理的に張り付いていること(常駐)を要求するものではありません。
技術者は、担当現場の職務(施工計画、工程管理、品質管理、安全管理、下請指導など)を適切に遂行できる限りにおいて、合理的な範囲で現場を離れることが認められています。
2現場を離れることが認められるケースと条件
では、具体的にどのような場合に、どの程度の期間、現場を離れることが許容されるのでしょうか。
国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」などを基に、その基準を解説します。
2-1. 短期間の離脱が認められる場合
現場の技術的な管理に支障がなく、発注者や元請負人と常に連絡が取れる状態であれば、以下のような理由による短期間(1~2日程度)の離脱は、問題ないとされています。
・ 会議や打ち合わせへの出席
・ 資材の調達や関係機関との協議
・ 専門的な知見を深めるための研修会や講習、試験への参加
・ 年次有給休暇などの休暇取得
・ その他、育児・介護休業など
2-2. 長期間の離脱が認められる場合
一週間程度の長期休暇など、「週の稼働日の半数以上」にわたり現場を離れる場合でも、一概に違反となるわけではありません。
この場合は、より厳格な条件として、発注者(元請工事の場合)の書面による承諾を得た上で、後述する「適切な施工ができる体制」を確保していれば、認められるとされています。
3最も重要な鍵
技術者が現場を離れる際に、必ず確保しなければならないのが、この「適切な施工ができる体制」です。
これは、主に以下の2つの要素から成り立ちます。
3-1. 連絡体制と現場復帰体制の確保
技術者が現場を離れている間も、電話やWEB会議システムなどで、現場の状況を把握し、必要な指示を出せる連絡体制が整っていることが必要です。
また、万が一の災害や事故が発生した際には、速やかに現場に戻れる復帰体制も求められます。
3-2. 代理の技術者の配置
より確実な方法が、技術者が不在の間の代理の技術者(代理人)を配置することです。
この代理人は、元の技術者と同等の資格や能力を持っている必要はありませんが、現場の状況を的確に把握し、元の技術者と円滑に連携できる人物であることが求められます。
重要なのは、適切な代理人を配置した場合は、元の技術者が「現場に戻り得る体制」までは不要とされる点です。
これにより、例えば遠隔地での研修参加など、より柔軟な対応が可能となります。
3-3. 忘れてはならない4つの注意点
これらの体制を整える上で、以下の4つの点には常に留意する必要があります。
① あくまで技術上の管理責任者は、元の主任技術者・監理技術者本人であること。
② 現場を離れることで、本来の職務(工程管理、品質管理など)に支障が生じることがないようにすること。
③ 休暇取得や研修参加は、労働者の権利であり、また企業の技術力向上に繋がる重要な機会です。会社は、これを不当に妨げることがないようにしなければなりません。
④ これらのルールは、建設業界における「ワーク・ライフ・バランス」の推進や、女性技術者の活躍促進といった、社会的な要請にも応えるためのものであるという視点を持つこと。
4整理
主任技術者・監理技術者の「専任」義務は、厳格なルールですが、それは決して技術者を現場に縛り付けるためのものではありません。
その本質は、工事の品質と安全に対する「責任体制の明確化」にあります。
法律の趣旨と具体的な運用ルールを正しく理解し、発注者との密なコミュニケーションを通じて、計画的に休暇や研修の機会を設けること。
そして、不在時にも現場が滞りなく進む「適切な施工体制」を構築すること。
こうした取り組みこそが、技術者の心身の健康とワーク・ライフ・バランスを守り、その能力を最大限に引き出し、ひいては企業の持続的な成長と、建設業界全体の魅力向上に繋がっていくのです。
5まとめ
建設現場における技術者の「専任」義務は、しばしば「常駐」義務と誤解されがちですが、法律の趣旨を正しく理解すれば、休暇の取得や研修への参加も可能です。
重要なのは、現場の管理体制を適切に構築し、発注者と明確な合意を形成しておくことです。
「自社の技術者配置や労務管理体制は、法的に問題ないだろうか」といったご不安は、ぜひ専門家にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令やガイドラインに基づき、コンプライアンスと効率的な経営を両立させる体制づくりをサポートします。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、貴社の「無限の可能性」を法務面から力強く支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/