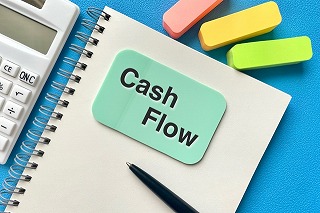「経審の結果通知書が届いたけど、数字がズラリと並んでいて、どこをどう見ればいいのか分からない…」
「P点という言葉は聞くけれど、それがどうやって決まるのか、自社の強みや弱点はどこにあるのか把握しきれない…」
「評点アップのために、具体的にどの項目に注力すべきか知りたい!」
こんなお悩みや疑問をお持ちではありませんか?
ご安心ください。
そのお悩み、この記事を読めば明確に解決できます。
経営事項審査(経審)の成果物である「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」。
この通知書に記載された各評価項目の意味を一つひとつ丁寧に読み解き、企業評価の仕組み、そして総合評定値(P点)アップに向けた具体的な戦略と対策を分かりやすく解説します。
今回の提案は、建設業許可を取得されている皆様が、経審結果通知書を深く理解し、それを経営改善と事業発展に繋げるためのお困りごとを解決する内容としてご紹介します。
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者にとって避けては通れない重要なプロセスです。
その審査結果が凝縮されているのが、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下、経審結果通知書)。
この通知書は、まさに企業の経営力や技術力を示す「成績表」であり、公共工事受注の可能性を左右するだけでなく、自社の経営状態を客観的に把握し、改善へと繋げるための貴重な情報源となります。
今回は、この経審結果通知書に記載されている主要な6つの評価軸について、その意味と重要性、そして評点アップのためのポイントを詳しく見ていきましょう。
1最重要指標:総合評定値(P点)
経審結果通知書の中で、まず目を通すべき最も重要な数値が「総合評定値」、通称「P点」です。
これは、企業の総合的な実力を示すスコアであり、公共工事の入札参加資格審査や業者の格付けにおいて、極めて重要な役割を果たします。
1-1. P点の位置づけと入札への影響力
P点は、後述する複数の評価項目の評点を、定められた計算式(P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W)に基づいて算出した総合的な評価値です。
多くの発注機関では、このP点を客観的な評価基準として採用しており、
・入札参加資格を得るための最低P点ラインを設定する(例:「P点〇〇点以上の業者に限る」)。
・P点に基づいて業者をA、B、Cといったランクに格付けし、入札可能な工事の規模(予定価格の上限・下限)を決定する。
といった形で活用されています。
つまり、P点が高ければ高いほど、より大規模で条件の良い公共工事の受注チャンスが広がるのです。
1-2. 構成要素の理解が不可欠
P点の数値そのものは非常に重要ですが、単に「P点が上がった・下がった」と一喜一憂するだけでは十分ではありません。
大切なのは、そのP点を構成している各評価項目(X1, X2, Y, Z, W)の内容をしっかりと把握し、自社のどの部分が評価され、どの部分に課題があるのかを分析することです。
それぞれの項目が企業のどのような側面を評価しているのかを理解することで、初めて具体的な経営改善策や評点アップ戦略を立てることが可能になります。
2完成工事高(X1)
「完成工事高(X1点)」は、申請した各建設業種における過去の工事売上高、つまり事業の規模を評価する項目です。
2-1. 評価の仕組み
基本的には、完成工事高が大きいほどX1点は高くなります。
評価は、業種ごとに行われ、申請する業種それぞれの完成工事高に応じて評点が算出されます。
国土交通省が定める評点テーブルに基づいて、完成工事高の金額帯ごとに点数が設定されています。
2-2. 評点算出の柔軟性
建設業の売上は、景気動向や大型案件の有無などによって、年ごとに大きく変動することがあります。
そのため、経審では、単年の完成工事高だけでなく、申請する事業年度を含む直近2年間または3年間の平均完成工事高のいずれか有利な方を選択して評価を受けることができます。
これにより、一時的な売上減少の影響を緩和し、より安定した事業規模評価が可能になります。
どちらの平均を選択すべきかは、各年の完成工事高の推移や、評点テーブルの区切りなどを考慮して慎重に判断する必要があります。
2-3. X1点向上のための視点
X1点を直接的に向上させるには、当然ながら受注を増やし、完成工事高を増大させることが基本となります。
しかし、単に売上を追求するだけでなく、利益率の高い工事を選別したり、得意分野を伸ばしたりといった戦略的な受注活動が求められます。
また、正確な工事経歴書の作成、適切な業種区分の適用なども、正当な評価を得るためには不可欠です。
3自己資本額及び利益額(X2)
「自己資本額及び利益額(X2点)」は、企業の財務的な安定性(体力)と、本業でどれだけ利益を生み出しているか(収益力)を評価する項目です。
これは、企業の持続可能性を示す重要な指標と言えます。
3-1.2つの要素
X2点は、大きく分けて以下の2つの要素から構成されています。
・ 自己資本額(純資産額):
企業のこれまでの利益の蓄積であり、返済義務のない安定した資金です。
貸借対照表の「純資産合計」の額が評価対象となります。自己資本が厚いほど、財務的な安定性が高いと評価されます。
・ 平均利益額:
企業の収益力を示す指標で、損益計算書の「営業利益」に、確定申告書別表十六等で確認できる「減価償却実施額」を加算して算出します。
単年度の利益だけでなく、過去複数年度(通常は2年間)の平均値が用いられることが一般的です。
3-2. X2点向上のための経営戦略
X2点を向上させるためには、以下の点が重要になります。
・ 利益体質の強化:
まずは、売上総利益(粗利)を確保し、販管費を適切にコントロールすることで、営業利益を安定的に計上できる体制を築くことが基本です。
・ 自己資本の充実:
獲得した利益を内部留保として積み上げ、自己資本を厚くしていくことが求められます。
安易な増資に頼るのではなく、継続的な利益創出が鍵となります。
・ 適切な減価償却:
減価償却費は費用として計上されますが、X2点の評価においては利益に加算されるため、法令に基づき適切に減価償却を行うことが重要です。
経営者は、短期的な売上だけでなく、長期的な視点で企業の財務体質を強化し、収益力を高める経営を意識する必要があります。
4経営状況(Y点)
経審結果通知書の一番下部に記載されている表が、「経営状況(Y点)」に関する詳細です。
このY点は、事前に民間の登録経営状況分析機関に申請し、発行された「経営状況分析結果通知書」に記載された評点がそのまま反映されます。
企業の財務的な健全性や効率性を多角的に評価する項目です。
4-1. 登録経営状況分析機関による詳細な分析
Y点は、以下の8つの財務指標に基づいて算出されます。
① 負債抵抗力に関する指標:
② 純支払利息比率(支払利息の負担度)
③ 負債回転期間(負債の支払い能力)
④ 収益性・効率性に関する指標:
⑤ 総資本売上総利益率(総資本に対する粗利率)
⑥ 売上高経常利益率(売上に対する経常利益率)
⑦ 財務健全性に関する指標:
⑧ 自己資本対固定資産比率(固定資産投資の健全性)
⑨ 自己資本比率(総資本に占める自己資本の割合)
⑩ 絶対的力量に関する指標:
⑪ 営業キャッシュフロー(現金創出力、2年平均)
⑫ 利益剰余金(内部留保の蓄積度)
これらの各指標について評点が算出され、それらを合算したものがY点となります。
4-2. Y点向上のための具体的なアプローチ
Y点を改善するためには、上記8つの指標それぞれに対する理解と対策が必要です。例えば、
・ 借入金を削減し支払利息を減らす(純支払利息比率の改善)。
・ 買掛金等の支払サイトを適切に管理する(負債回転期間の適正化)。
・ 粗利率の高い工事を選別・受注する(総資本売上総利益率の向上)。
・ 固定資産への過度な投資を避け、自己資本に見合った投資を行う(自己資本対固定資産比率の改善)。
・ 利益を確保し内部留保を増やす(自己資本比率、利益剰余金の増加)。
・ 黒字経営を継続し、営業キャッシュフローをプラスに保つ(営業キャッシュフローの改善)。
これらの対策は一朝一夕に達成できるものではなく、日々の堅実な経営管理と財務戦略が求められます。
5技術力(Z点)
「技術力(Z点)」は、その名の通り、建設業者の技術的な能力を評価する項目です。
主に「技術職員数」と「元請完成工事高」の2つの側面から評価されます。
5-1. 技術職員数
審査基準日(通常は決算日)時点で、企業に在籍している有資格技術職員の数とその資格の種類によって評価されます。
・ 資格の種類:
1級国家資格者(例:1級建築士、1級土木施工管理技士など)、監理技術者資格者証保有者、基幹技能者、2級国家資格者(実務経験による加点あり)など、資格の種類や実務経験に応じて評価点数が異なります。より上位の資格を持つ技術者が多いほど、評価は高くなります。
・ 業種ごとのカウント:
一人の技術職員が複数の業種の資格を持っている場合でも、経審の加点対象となるのは原則として2業種までです。
どの業種で技術職員をカウントさせるかは、戦略的に選択する必要があります。
技術者の確保と育成、資格取得の奨励は、Z点向上に直結する重要な取り組みです。
5-2. 元請完成工事高の評価
Z点の評価には、X1点(完成工事高)とは別に、元請として完成させた工事の年間平均完成工事高も含まれます。
これは、下請工事だけでなく、発注者から直接工事を請け負い、施工管理能力を発揮できる企業を評価するものです。
元請工事の実績を増やすことが、この部分の評点アップに繋がります。
6その他審査項目(社会性等)(W点)
経審結果通知書の最も右側に記載される表が、「その他審査項目(社会性等)(W点)」に関する部分です。
これは、企業が法令を遵守し、労働環境の整備や地域貢献など、社会的責任をどの程度果たしているかを評価する項目群です。
近年、建設業界におけるコンプライアンス意識の高まりや、担い手確保の重要性から、W点の比重は増す傾向にあります。
6-1. 多岐にわたる評価項目
W点は、非常に多くの評価項目から構成されています。主なものは以下の通りです。
・ 労働福祉の状況:
雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入状況、建設業退職金共済制度(建退共)への加入・履行状況、退職一時金制度または企業年金制度の導入状況、法定外労働災害補償制度への加入状況。
・ 建設業の営業継続の状況: 営業年数。
・ 防災活動への貢献の状況: 地方公共団体等との防災協定締結の有無。
・ 法令遵守の状況: 過去の指示処分・営業停止処分の有無。
・ 建設機械の保有状況: 自社で保有する一定の建設機械の台数や種類。
・ 国際標準化機構(ISO)登録の状況: ISO9001(品質マネジメント)、ISO14001(環境マネジメント)の認証取得状況。
・ 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況: 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況(レベルに応じた技能者の数)、認定職業訓練の実施状況、若手技術者(35歳未満)の数、新規若手技術者(学卒後3年以内または29歳以下で入職後3年以内)の数など。
・ 研究開発の状況: 会計監査人の設置、研究開発費の額。
・ 建設工事の安全衛生に関する取り組みの状況(新設予定): 安全衛生優良企業認定(ホワイトマーク)など。
これらの各項目について、基準を満たしていれば加点されます。
6-2. W点向上のための取り組み
W点を向上させるためには、社会保険への適切な加入はもとより、建退共への加入・履行、防災協定の締結、ISO認証の取得、そして近年特に重視されている若手人材の育成(CCUSの活用や資格取得支援など)や働き方改革への積極的な取り組みが求められます。
これらは、単に経審の評点を上げるだけでなく、企業の持続的な成長、従業員満足度の向上、そして社会からの信頼獲得にも繋がる重要な経営課題です。
7重要ポイントと次への戦略
経審結果通知書を受け取ったら、P点だけでなく、それを構成するX1, X2, Y, Z, Wの各評点、さらにはY点やW点を構成する個々の項目まで細かく確認することが肝要です。
7-1. 強みと弱みの客観的把握
どの項目で高い評価を得ていて、どの項目が平均よりも低いのかを把握することで、自社の強みと弱みを客観的に認識できます。
これが経営改善の第一歩です。
7-2. 重点改善項目の特定(X2、Y、W)
ユーザー様ご提供の本文にもありましたが、特に企業全体の経営体質や持続可能性という観点からは、「X2点(自己資本額及び利益額)」「Y点(経営状況)」「W点(その他審査項目・社会性等)」の3つが極めて重要です。
⑴ X2点は企業の基本的な体力と稼ぐ力を示します。
⑵ Y点は財務の健全性と効率性を示し、金融機関からの信用にも直結します。
⑶ W点は法令遵守、労働環境、地域貢献といった企業の社会的信頼性を示し、近年その重要性はますます高まっています。
X1点(完成工事高)やZ点(技術力)ももちろん重要ですが、これらは受注状況や技術者の在籍状況に左右されやすい側面があります。
一方で、X2点、Y点、W点は、日々の堅実な経営努力や体制整備の積み重ねによって改善されるものであり、企業の「質」をより直接的に反映すると言えるでしょう。
したがって、中長期的な視点に立ち、これら3つの評価軸を意識した経営戦略を立て、具体的な改善策を実行していくことが、持続的なP点アップ、そして企業の成長に繋がります。
7-3. 専門家(行政書士)活用のすすめ
経審の評点分析、改善策の立案、そして次期経審に向けた準備は、専門的な知識と経験を要します。
どの項目をどのように改善すれば効果的にP点アップに繋がるのか、最新の評価基準や法改正にどう対応すべきかなど、自社だけで判断するのは難しい場合も少なくありません。
経験豊富な行政書士は、経審結果通知書を詳細に分析し、お客様の状況に合わせた最適な評点アップ戦略をご提案できます。
また、煩雑な申請書類の作成代行はもちろん、経営改善に関するアドバイスや、W点対策としての各種制度導入サポートなども行っています。
8まとめ
P点という総合評価はもちろん重要ですが、その内訳であるX1, X2, Y, Z, Wの各項目、さらにはY点やW点を構成する細かな評価要素一つひとつに、貴社の強みや改善すべき課題が隠されています。
建設業許可申請や経営事項審査(経審)は、公共工事の元請業者として事業を展開し、企業をさらに成長させていくためには、絶対に欠かせない重要な手続きです。
しかし、その制度の複雑さ、評価項目の多さ、そして毎年のように行われる細かな改正により、「どこをどう見れば良いのか…」「どうすれば評点が上がるのか…」「自社だけでの対応は限界を感じる…」といったお悩みを抱えていらっしゃる経営者様、ご担当者様は決して少なくありません。
当事務所は、岩手県北上市を拠点に、全国の建設業者様の建設業許可・経営事項審査(経審)を専門的にサポートする行政書士事務所です。
私たちは、お客様からお預かりした経審結果通知書を徹底的に分析し、現状の強みと弱みを明確化します。
その上で、お客様の事業規模や経営方針、目標とするP点などを総合的に勘案し、最も効果的かつ実現可能な評点アップ戦略、そして具体的な経営改善策をご提案させていただきます。
煩雑な書類作成から申請代行、行政機関との折衝まで、責任を持って一貫してサポートいたします。
法律の規定や申請手続き、評価基準は、専門家でなければなかなか理解しにくいものです。
ご自身で貴重な時間を費やして情報収集や対策検討をされるよりも、日々最新の動向を把握し、豊富な実務経験を持つ専門家にご相談いただく方が、結果として時間的にもコスト的にも効率が良く、そして確実な成果に繋がります。
また、当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーといった、各分野のプロフェッショナルと連携する『士業の会』を主宰している点です。
さらに、元岩手県職員として企業誘致や県立大学新設といった行政実務に深く携わった経験がございます。
岩手県内はもちろん、全国の建設業者様で、経営事項審査(経審)の評点アップや、建設業許可の新規取得・更新をご検討されているのであれば、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
貴社の輝かしい未来への航海を、力強くサポートいたします。
9お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/