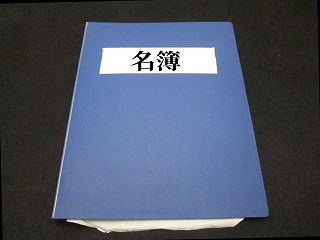「作成した施工体制台帳は、いつまで現場に置いておけばいいの?」
「民間工事でも、発注者に提出する義務はあるのだろうか?」
「工事が終わったら、台帳はもう捨てても良い?」
こんな、施工体制台帳の「その後」に関する疑問をお持ちではありませんか?
ご安心ください。
その疑問は、建設業法が定める施工体制台帳の、作成後の管理ルールを正しく理解することで解決できます。
この記事では、元請負人の皆様が知っておくべき施工体制台帳の管理について、「現場での備置き」「提出・閲覧」「営業所での保存」という3つのフェーズに分けて、分かりやすく解説します。
元請負人が作成する「施工体制台帳」は、工事現場の透明性を確保し、適正な施工体制を築くための、建設業コンプライアンスの根幹をなす重要書類です。
しかし、その重要性は、単に「作成すること」だけで終わりではありません。法律は、作成された台帳を、工事の各段階に応じて、どのように管理・運用すべきかについても、明確なルールを定めています。
この管理ルールを正しく理解し、実践することは、元請負人としての責任を全うし、企業の信頼性を内外に示す上で不可欠です。
今回は、施工体制台帳の「作成後」に焦点を当て、その管理・保管に関するルールを詳しく見ていきましょう。
1フェーズ①:工事期間中の「現場への備置き」義務
まず、工事が行われている期間中の、最も基本的なルールです。
1-1. 工事完成・引渡しまでの間の義務
施工体制台帳の作成義務がある工事において、元請負人は、その工事の目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場ごと(または、工事現場を管轄する営業所)に、その台帳を備え置かなければなりません。
これは、発注者や監督員、そして行政庁の立ち入り検査などがあった際に、いつでも現場の施工体制を提示できるようにしておくための、非常に重要な義務です。
1-2. 備置きの目的
現場に台帳を備え置くことは、元請負人が常に最新の施工体制を把握し、管理しているという証になります。
また、下請負人から提出される「再下請負通知書」に基づき、内容を随時更新し、常に正確な状態を保っておく必要があります。
2フェーズ②:発注者への「提出・閲覧」に関するルール
次に、作成した台帳を発注者(注文者)にどのように開示するかについてのルールです。
これは、公共工事と民間工事で扱いが異なります。
2-1. 公共工事の場合:「提出」が原則
国や地方公共団体が発注する公共工事においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」の規定により、元請負人は、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出する義務があります。
2-2. 【重要】ICT活用による提出の「不要化」
ここで、非常に重要な法改正の情報があります。
建設業界のDX化を推進するため、2024年(令和6年)12月から施行される改正入札契約適正化法により、建設キャリアアップシステム(CCUS)などを活用し、発注者がオンラインで施工体制を確認できる措置を講じた場合は、施工体制台帳の写しの提出が不要となります。
これは、書類作成・提出業務の負担を大幅に軽減する、画期的なルール変更です。
2-3. 民間工事の場合:「閲覧」の義務
一方、民間工事においては、公共工事のような提出義務は法律上ありません。
ただし、建設業法第24条の8第4項では、発注者から請求があった場合は、元請負人は、その施工体制台帳を発注者の閲覧に供しなければならない、と定めています。
請求があったにもかかわらず、正当な理由なく閲覧を拒否することは、法令違反となります。
2-4. 施工体系図の取り扱い
なお、施工体制台帳とセットで作成される「施工体系図」については、あくまで「現場への掲示」が義務であり、発注者への提出義務はありません。
3フェーズ③:工事完了後の「営業所での保存」義務
工事が無事に完了し、目的物を発注者に引き渡した後も、元請負人の責任が終わるわけではありません。
3-1. 営業所での「5年間」の保存義務
建設業法では、建設業者はその営業に関する図書として、施工体制台帳を営業所に5年間保存することが義務付けられています。
工事が完了したからといって、すぐに台帳を破棄することはできません。
3-2. 添付書類も一体として保存
この保存義務は、施工体制台帳本体だけでなく、その添付書類(下請契約書の写し、技術者の資格者証の写しなど)も対象となります。
台帳と添付書類は、法律上「一体の書類」として扱われるため、必ず一緒にファイリングし、保管するようにしてください。
3-3. 保存の目的
なぜ、工事完了後も長期間の保存が求められるのでしょうか。
これは、将来、その工事に関して何らかのトラブル(瑕疵の発生など)が起きた際に、当時の施工体制や責任の所在を客観的に証明するための、重要な証拠書類となるからです。
適切な保存は、将来の紛争リスクから会社を守るための、重要なリスク管理の一環なのです。
4整理
施工体制台帳の管理は、工事の開始前から、その完成後5年という長期間にわたる、元請負人の息の長い責務です。
現場での備置き、適切な開示、そして営業所での長期保存。これら一連のルールを誠実に遵守することは、単なるコンプライアンス対応に留まりません。
それは、自社が行った工事の記録を、責任をもって後世に残すということであり、企業の「信頼の歴史」そのものを築き上げていく作業と言えるでしょう。
5まとめ
施工体制台帳は、作成して終わり、ではありません。
工事期間中は現場に備え置き、公共工事では発注者に提出し、そして工事完了後は営業所で5年間保存するという、長期にわたる管理義務が法律で定められています。
この管理ルールを正しく理解し、実践することは、元請負人としての責任を果たし、企業の信頼性を内外に示す上で不可欠です。
「自社の書類管理体制は、法的に問題ないだろうか」と少しでも不安に感じたら、専門家にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令に基づき、適正な書類作成から、その後の適切な管理・保存方法まで、トータルでサポートします。
元岩手県職員としての経験も活かし、貴社の健全な事業運営を力強く支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/


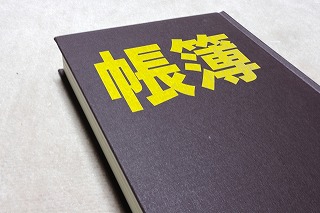

.jpg)