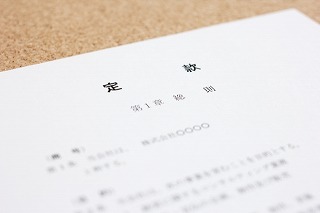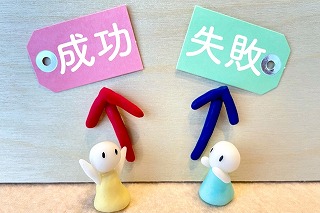「医療法人にはどんな種類があるの?」
「社団医療法人と財団医療法人の違いは?」
「持分あり・なしって何?」
「社会医療法人になると、どんなメリットがあるの?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?
医療法人には、社団医療法人、財団医療法人、特定医療法人、社会医療法人など、さまざまな種類があり、それぞれ設立要件や運営方法、税制上の取り扱いなどが異なります。
また、法改正により、新たに創設された制度や、経過措置が設けられている制度などもあり、医療法人制度は非常に複雑です。
ご安心ください!
今回の記事では、医療法人の種類や区分について、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、医療法人の全体像が理解でき、あなたのクリニックや病院に最適な法人形態を選ぶための第一歩を踏み出せます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で医療機関の開設・運営に携わる皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1医療法人とは?
医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、または介護老人保健施設、介護医療院を開設・運営することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。
個人開業の診療所は、医師または歯科医師個人が経営者となりますが、医療法人は、法人格を持つため、財産や契約関係が個人とは分離されます。
これにより、事業の継続性や社会的信用を高めることができます。
2医療法人の種類
医療法人は、大きく「社団医療法人」と「財団医療法人」の2つに分けられます。
これは、一般の法人における「社団法人」と「財団法人」の区別に対応するものです。
2-1. 社団医療法人
社団医療法人は、複数の人が集まり、資金や不動産、医療機器などの財産を出し合って設立する法人です。
株式会社のように、「社員」と呼ばれる構成員が意思決定に関与します。
現在の医療法人の大半は、この社団医療法人です。
〇特徴:
・複数の人(社員)が出資して設立
・社員総会が最高意思決定機関
・定款で定められた範囲内で、事業運営の自由度が高い
・剰余金の配当はできない(非営利性)
2-2. 財団医療法人
財団医療法人は、個人または法人が寄付した財産を運用して、医療事業を行う法人です。
寄付された財産が基本となるため、設立には一定額以上の財産が必要となります。
また、意思決定は、理事会や評議員会によって行われます。
〇特徴:
・個人または法人が寄付した財産を基に設立
・理事会や評議員会が意思決定機関
・公益性が高い
・設立要件が厳しい(一定額以上の財産が必要)
3社団医療法人の区分(持分あり・持分なし)
社団医療法人は、さらに「持分の定めのある社団医療法人(持分あり医療法人)」と「持分の定めのない社団医療法人(持分なし医療法人)」に分けられます。
この「持分」とは、株式会社の株式に似た概念で、医療法人に対する出資者の権利(財産権)を表すものです。
3-1. 持分あり医療法人
持分あり医療法人は、設立時に出資した社員が、出資額に応じて「持分」を持つ法人です。
社員が退社する際や、医療法人が解散する際には、持分の払い戻しを請求することができます。
〇特徴:
・社員に出資持分がある
・社員の退社時や法人解散時に、持分の払い戻し請求権がある
・相続税の課税対象となる
3-2. 持分なし医療法人
持分なし医療法人は、社員に出資持分がない法人です。
社員が退社する際や、医療法人が解散する際に、持分の払い戻しを請求することはできません。
法人の解散時の残余財産は、国や地方公共団体、他の医療法人などに帰属することになります。
〇特徴:
・社員に出資持分がない
・持分の払い戻し請求権がない
・相続税の課税対象とならない(出資持分がないため)
3-3. 医療法改正と持分あり医療法人
平成18年(2006年)の医療法改正により、持分あり医療法人の新規設立は認められなくなりました。
これは、医療法人の非営利性を徹底し、経営の透明化を図るためです。
現在存在する持分あり医療法人は、法改正前の経過措置として存続が認められているものであり、「経過措置型医療法人」と呼ばれています。
国は、経過措置型医療法人に対し、持分なし医療法人への移行を促しています。
3-4. 出資額限度法人
持分あり医療法人のうち、社員の退社時または解散時の払戻額の上限を、実際の出資額と同額にとどめる旨の定款を持つ法人を「出資額限度法人」といいます。
出資額限度法人は、持分あり医療法人の中間的な形態であり、持分なし医療法人への移行を円滑に進めるための措置として設けられました。
4基金拠出型法人
平成18年の医療法改正以降に設立された医療法人(持分なし医療法人)は、原則として「基金拠出型法人」となります。
基金拠出型法人とは、法人の資金調達手段として、「基金」制度を導入している法人です。
4-1. 基金とは?
基金とは、医療法人に拠出された金銭その他の財産であり、医療法人が拠出者に対して、定款の定めに従い返還義務を負うものです。
株式会社の株式とは異なり、基金には配当はありません。
また、基金の返還には、一定の制限があります。
4-2. 基金制度のメリット
(1)資金調達の多様化:
医療法人は、寄付だけでなく、基金の拠出を募ることにより、資金調達の手段を多様化できます。
(2)経営の安定化:
基金は、返還義務があるものの、長期的な資金として活用できるため、医療法人の経営の安定化に繋がります。
5公益性の高い医療法人
医療法人の中には、より公益性の高い医療を提供する法人として、税制上の優遇措置などが認められている法人があります。
それが、「特定医療法人」と「社会医療法人」です。
5-1. 特定医療法人
特定医療法人は、租税特別措置法に基づき、国税庁長官の承認を受けた医療法人です。
特定医療法人には、法人税の軽減税率が適用されるなどの税制上の優遇措置があります。
〇承認要件(主なもの):
・公益性が高いこと(同族支配でないことなど)
・事業運営が適正であること
・法令に違反する事実などがないこと
5-2. 社会医療法人
社会医療法人は、平成18年の医療法改正により創設された、より公益性の高い医療法人です。
都道府県知事の認定を受けることで、税制上の優遇措置や収益業務の実施、附帯事業範囲の拡大などが認められます。
〇認定要件(主なもの):
・へき地医療、救急医療、災害医療、周産期医療、小児救急医療など、地域で特に必要とされる医療を提供していること
・公益性が高いこと(同族支配でないことなど)
・運営が適正であること
・財務状況が良好であること
〇税制上の優遇措置:
・法人税の軽減税率
・固定資産税の非課税
・不動産取得税の非課税 など
〇収益業務:
・社会医療法人は、本来業務に支障のない範囲で、収益業務を行うことができます。
・収益業務の例:駐車場経営、売店経営、不動産賃貸など
〇附帯業務範囲の拡大:
・通常の医療法人よりも広い範囲の附帯業務が認められます。
・例:介護保険サービス、有料老人ホームなど
6広域医療法人
広域医療法人とは、2つ以上の都道府県に、病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設する医療法人です。
広域医療法人は、より広域的な視点から、地域医療の連携や医療資源の効率的な活用に貢献することが期待されています。
7「一人医師医療法人」
昭和60年(1985年)の医療法改正により、医師または歯科医師が1人でも医療法人を設立できるようになりました。
これを「一人医師医療法人」といいます。
(1)メリット:
・事業承継がしやすい
・節税効果がある場合がある
・社会的信用が高まる
(2)デメリット:
・事務手続きが煩雑になる
・社会保険料の負担が増える場合がある
8まとめ
医療法人には、様々な種類や区分があり、それぞれ設立要件や運営方法、税制上の取り扱いなどが異なります。
自院の状況や将来の展望に合わせて、最適な法人形態を選択することが重要です。
医療法人の設立・運営は、専門的な知識が必要となる場面が多く、手続きも煩雑です。
「どの種類の医療法人が自院に合っているのか分からない」「設立手続きが複雑で、何から手を付けていいか分からない」など、お困りの場合は、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、医療法人の設立・運営に関する専門家であり、書類作成から行政庁との交渉、設立後のサポートまで、トータルでサポートすることができます。
特に、医療法人の設立には、都道府県知事の認可が必要であり、提出書類も多岐にわたるため、専門家のサポートが不可欠です。
当事務所では、医療法人設立・運営に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
医療法人設立・運営に関するお悩みは、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
9お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ